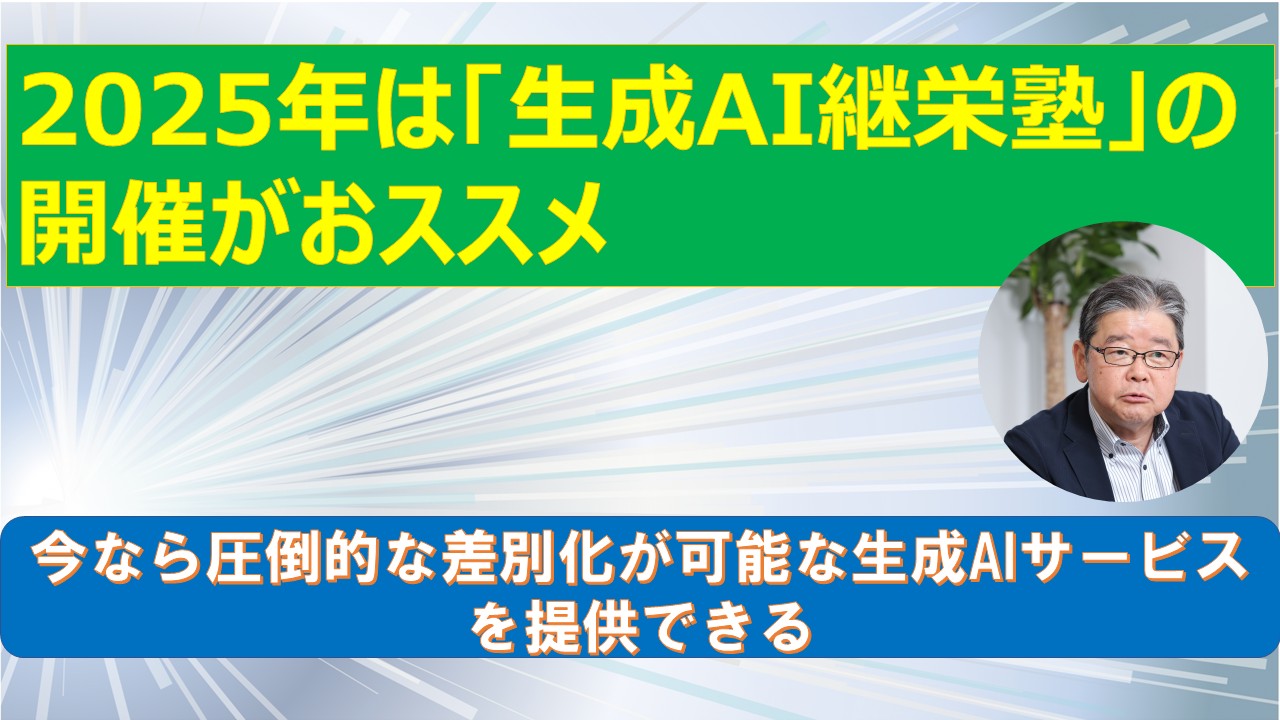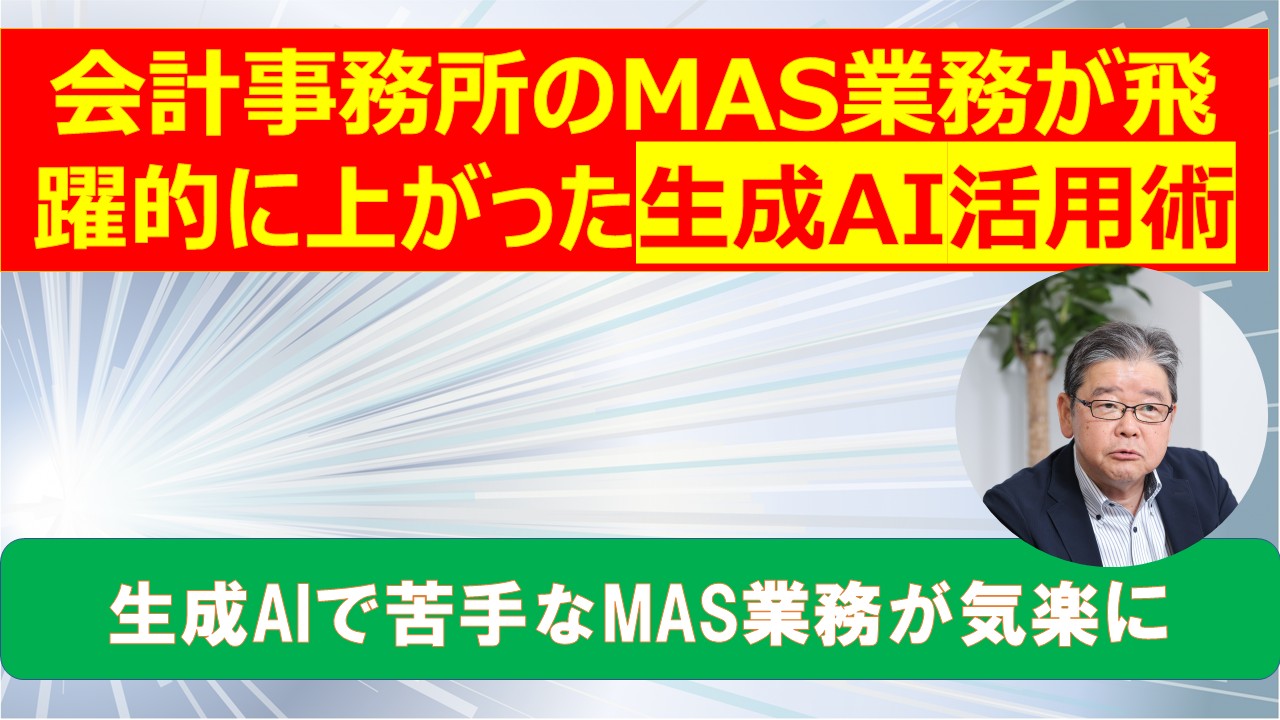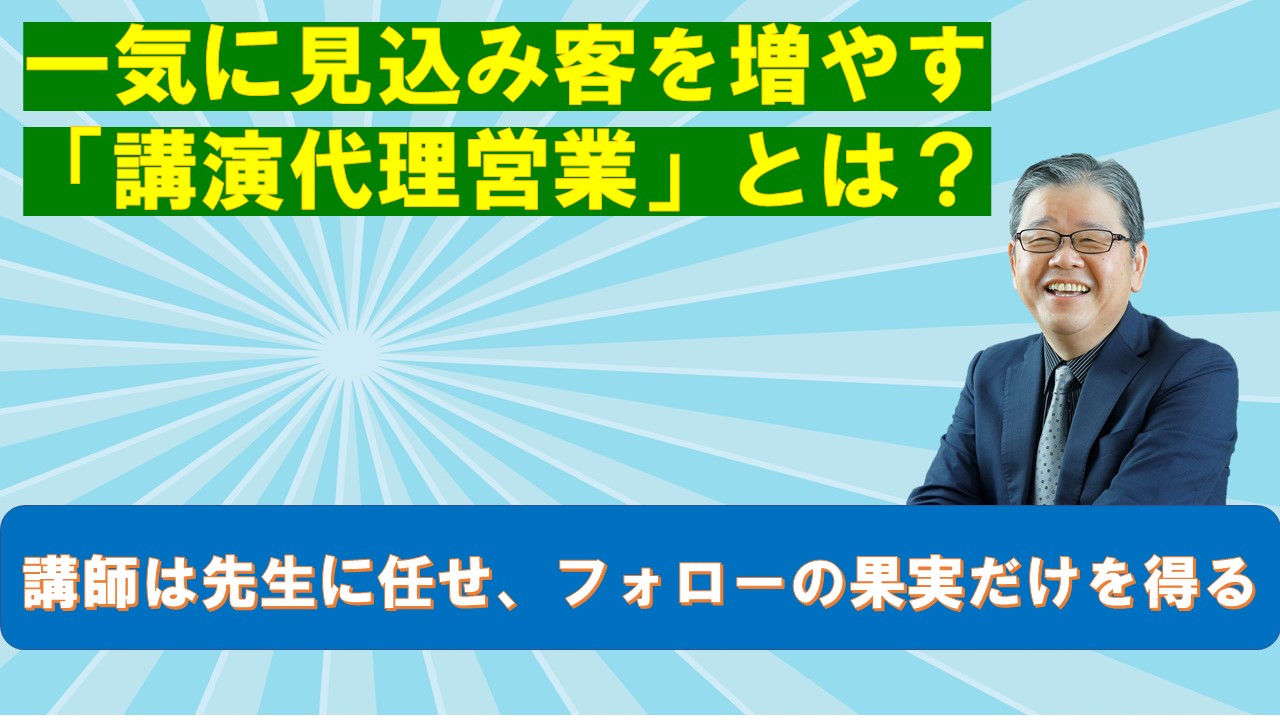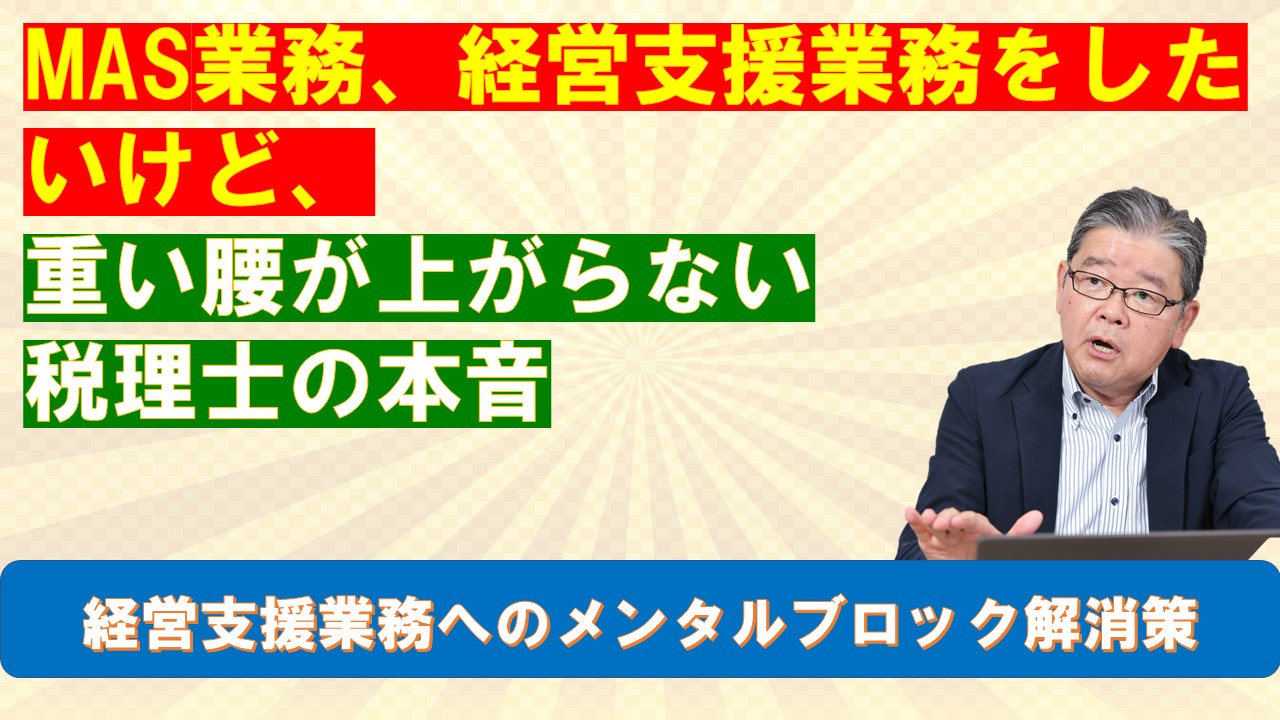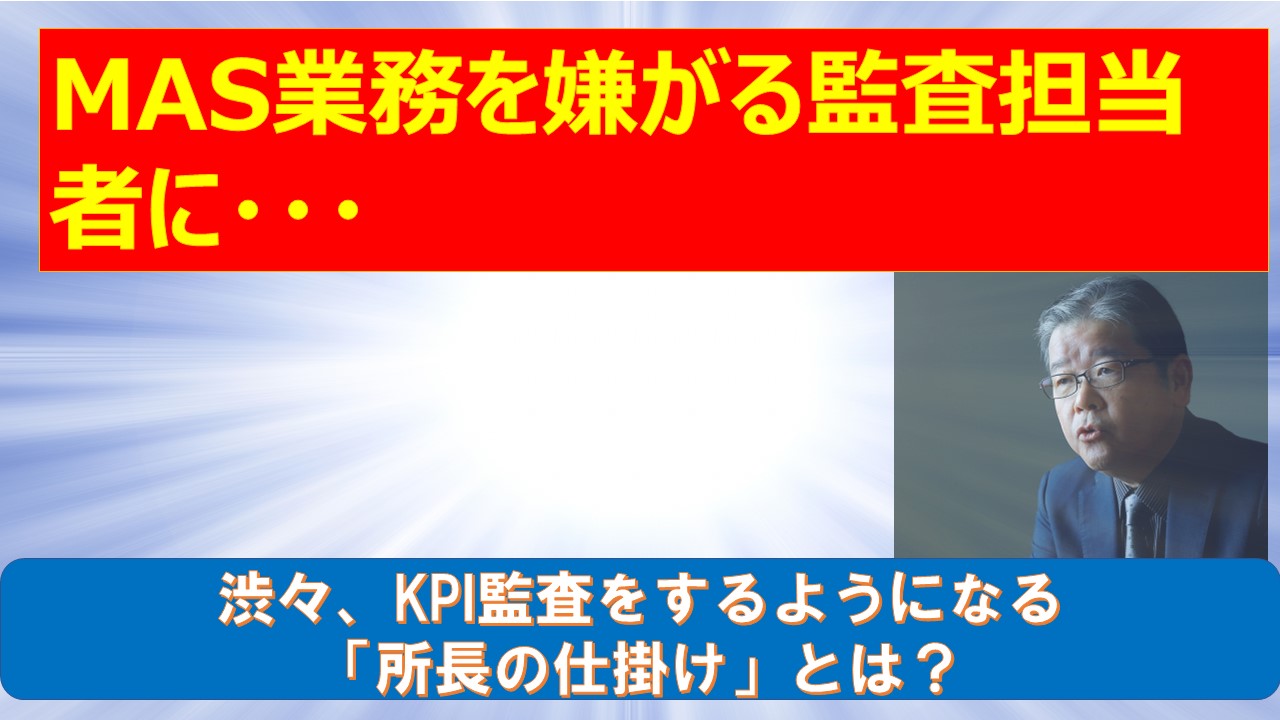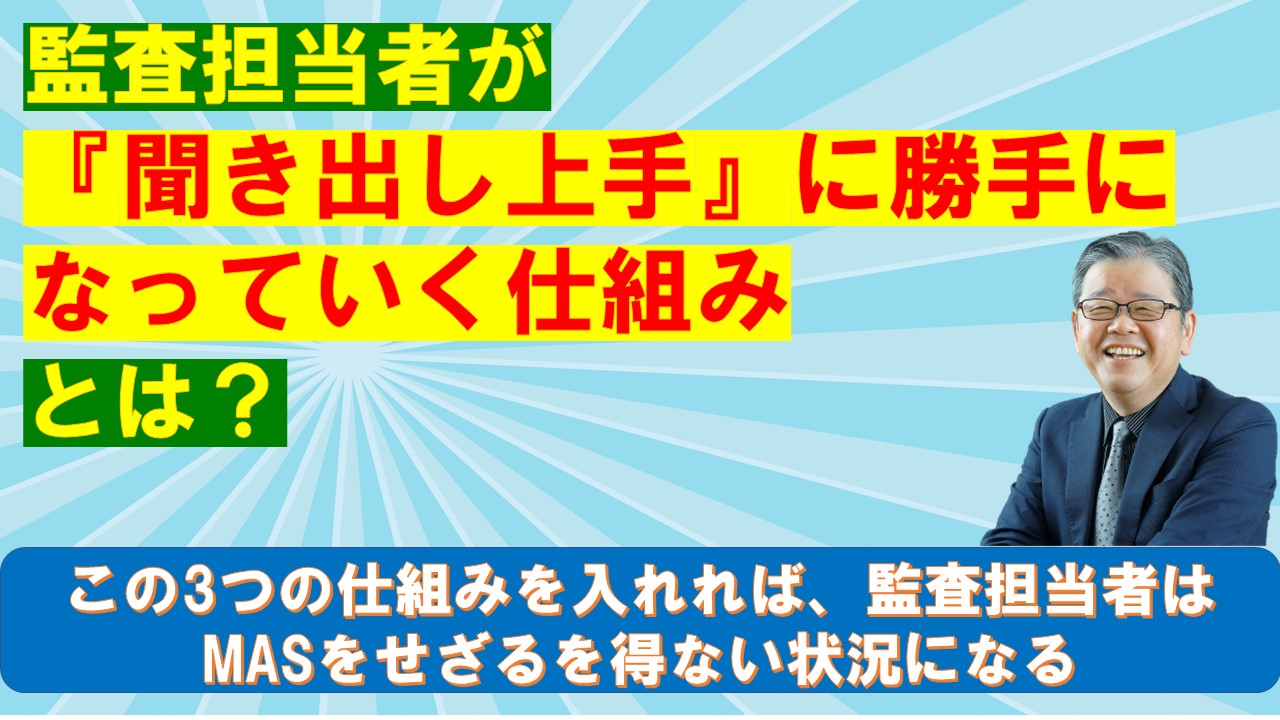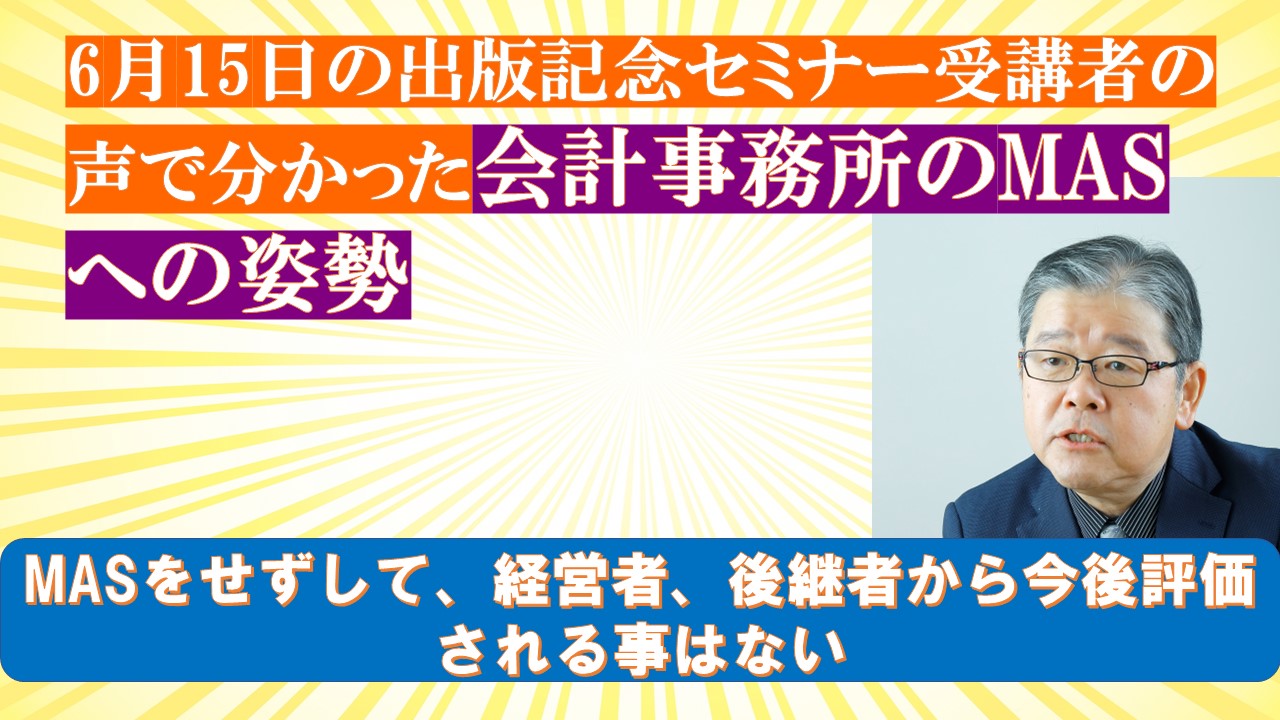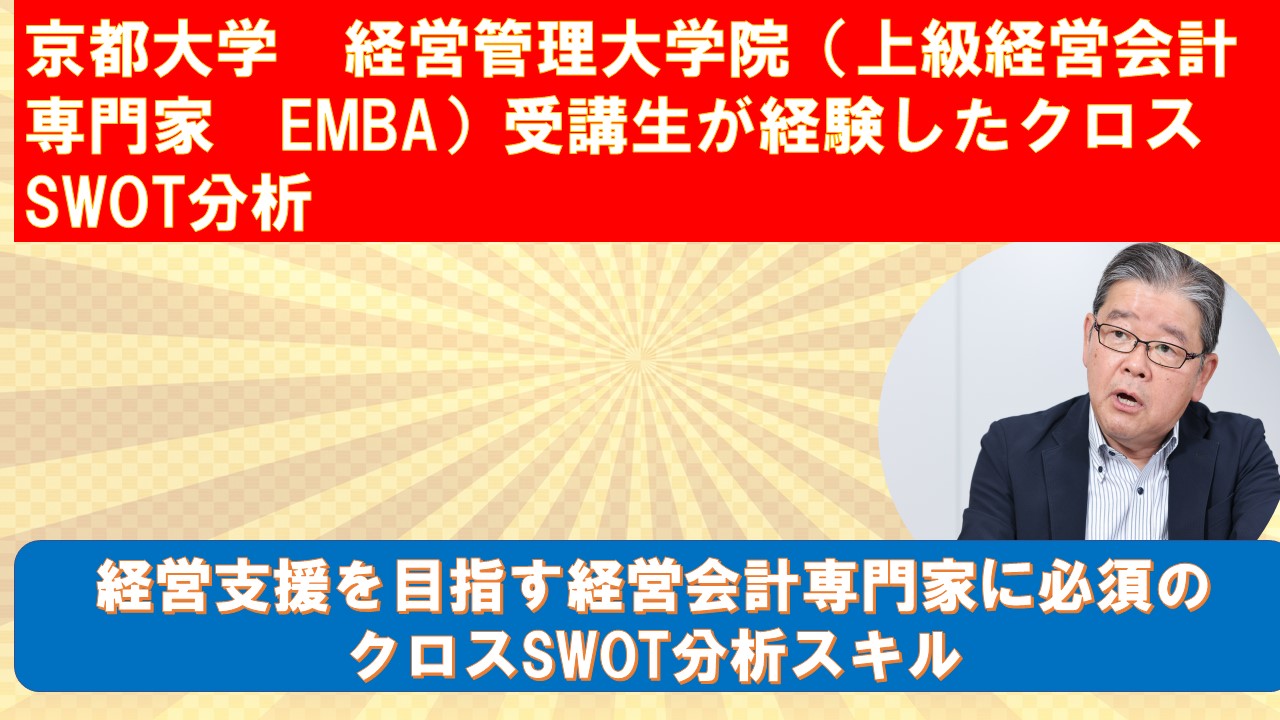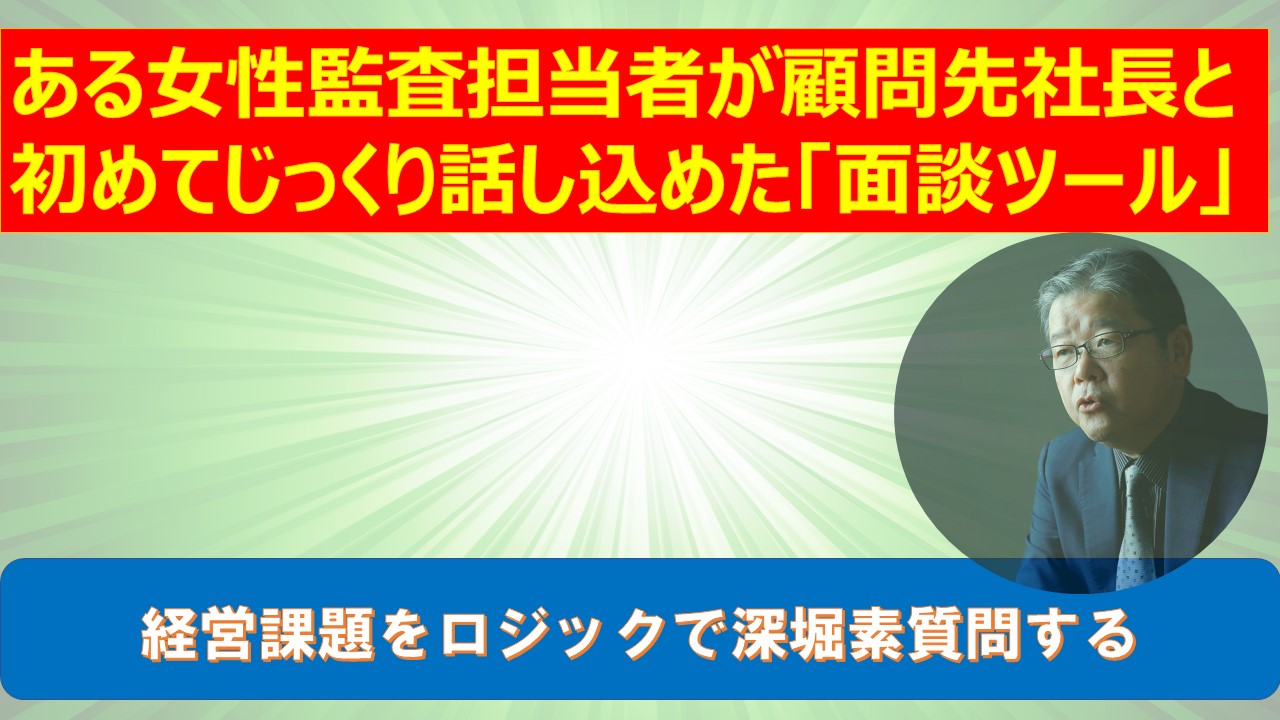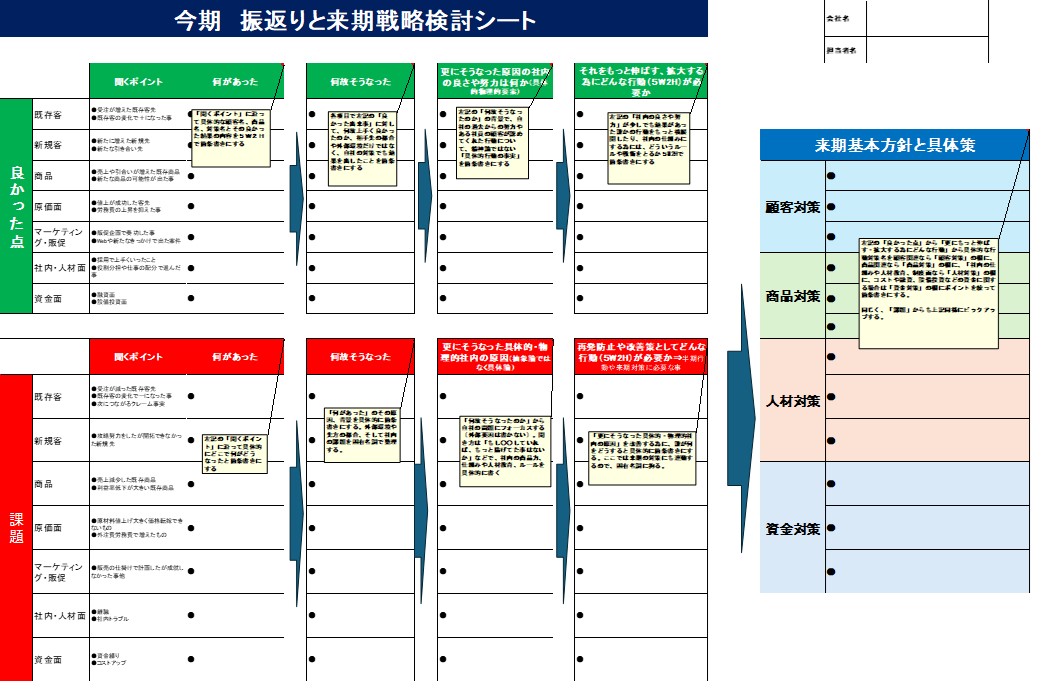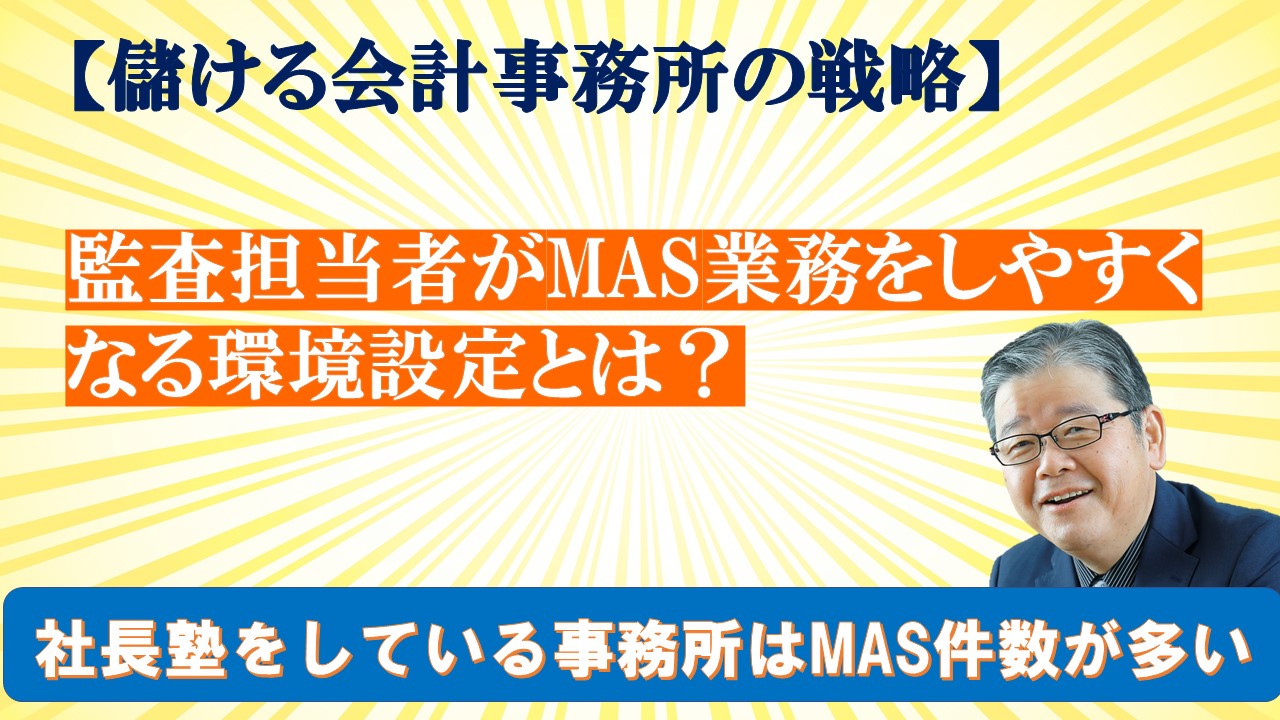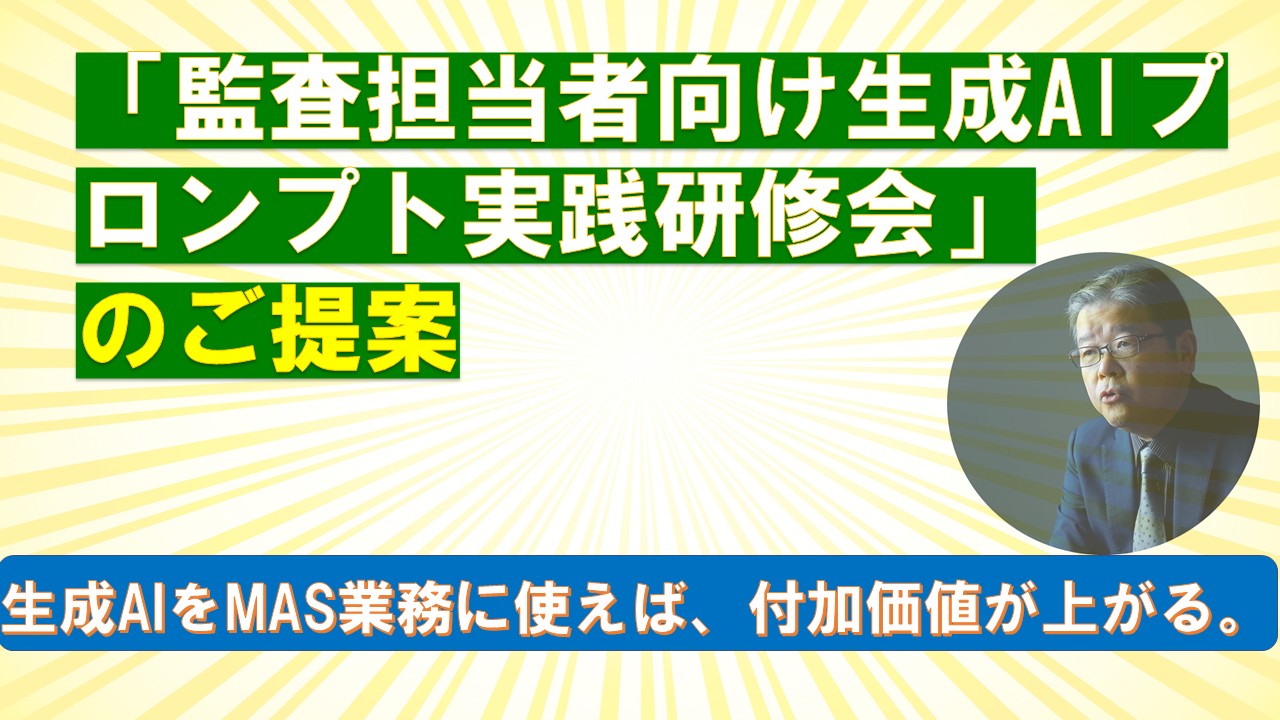

今、会計事務所が主催し顧問先や見込み先の経営者、後継者を集める「生成AI継栄塾」の引き合いが増えています。
ところが、肝心な案内をする監査担当者が「生成AIで何ができるのか、顧問先に上手く説明できない」と言う事態になっている事務所もあります。
これは困った事だという事で、まず監査担当者向けに「生成AIを活用したMAS支援」の中身を体験してもらわなければ話になりません。
そこで、まずは所内の監査担当者向けに「生成AIを活用した経営支援」のアウトプットを経験してもらうのが、『監査担当者向け生成AIプロンプト実践研修会」です。