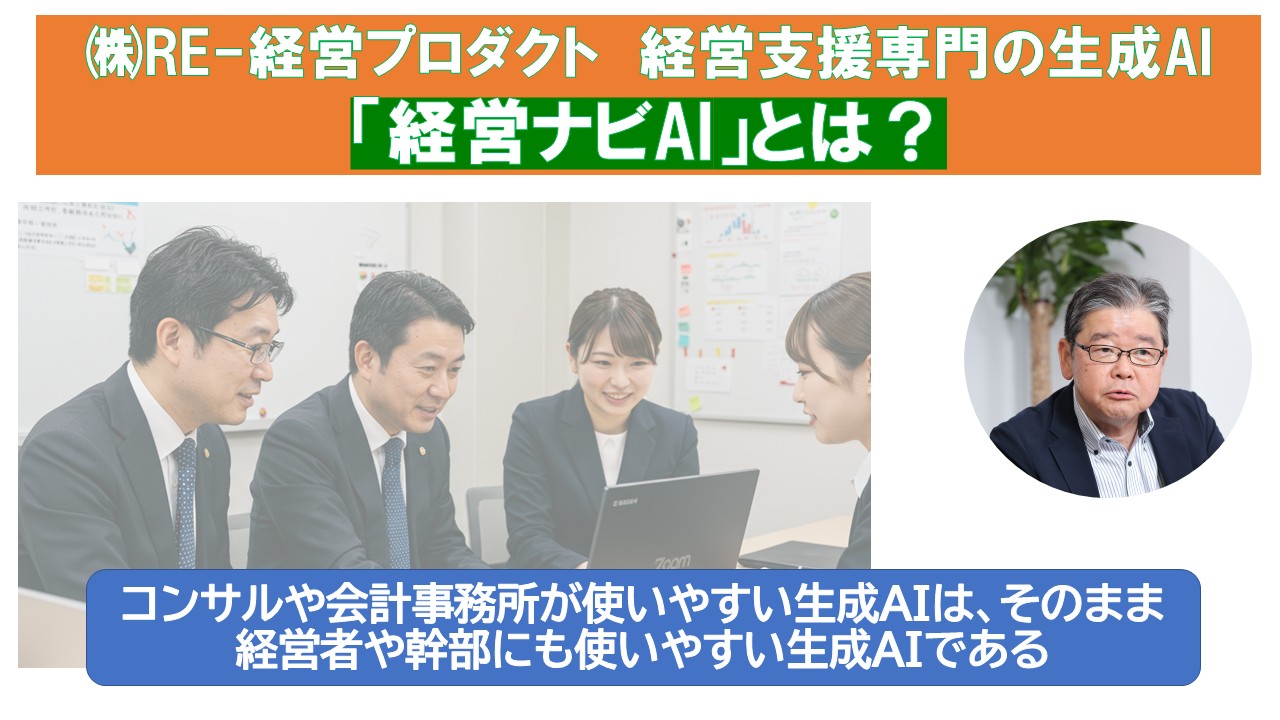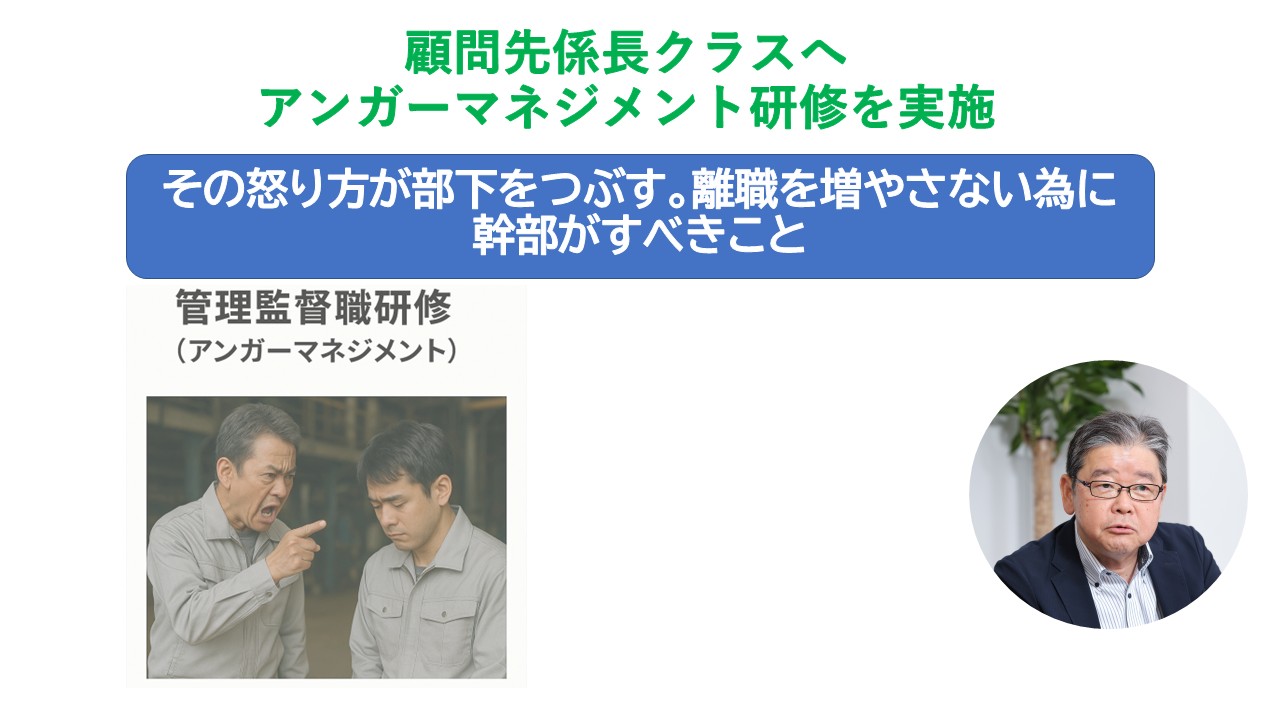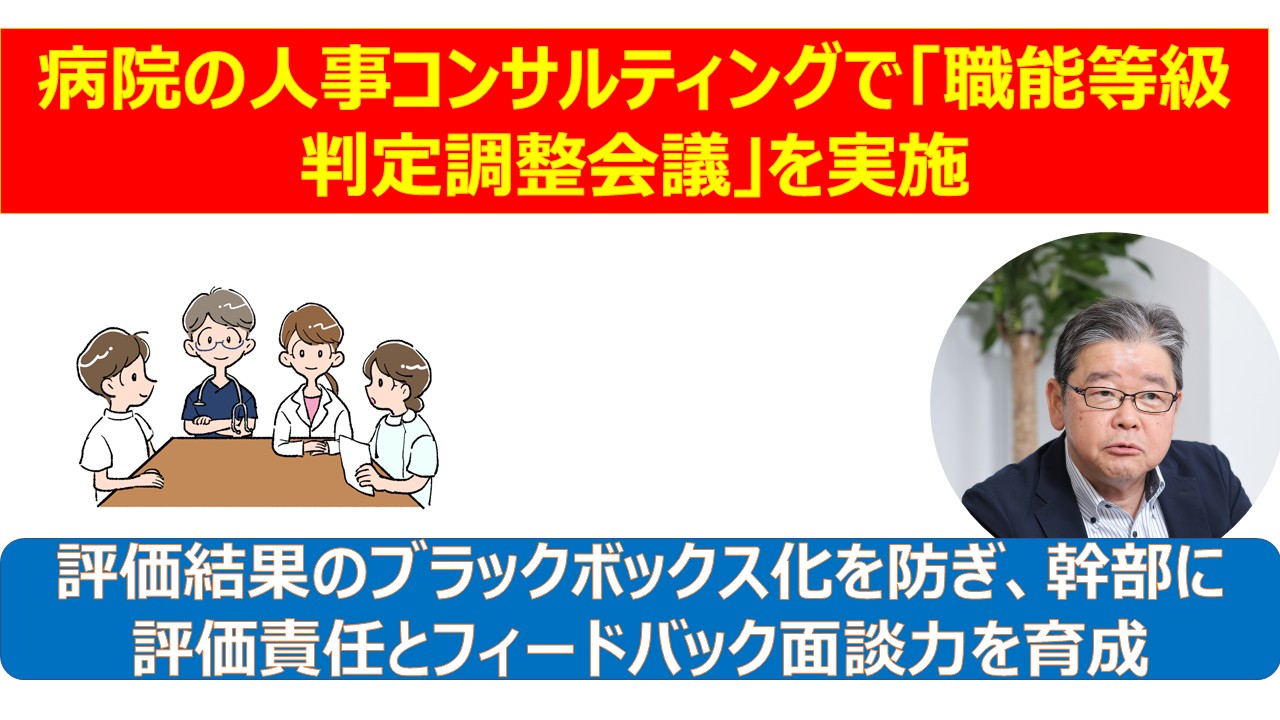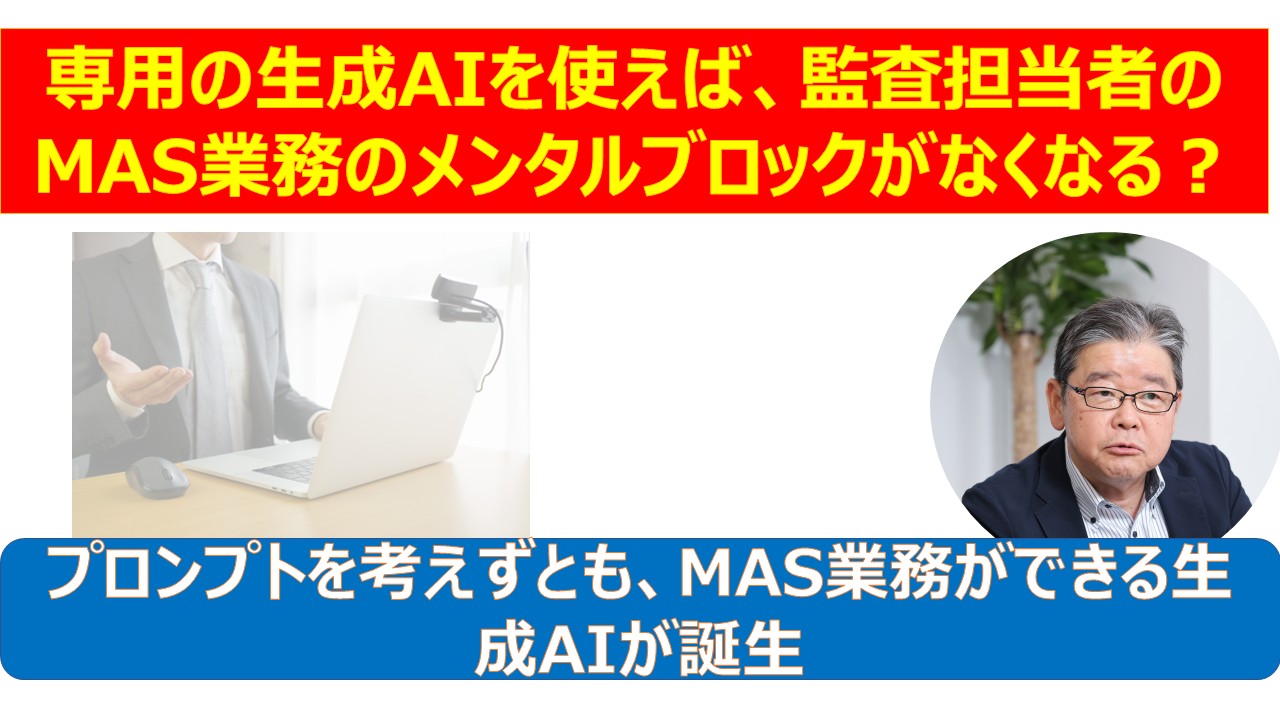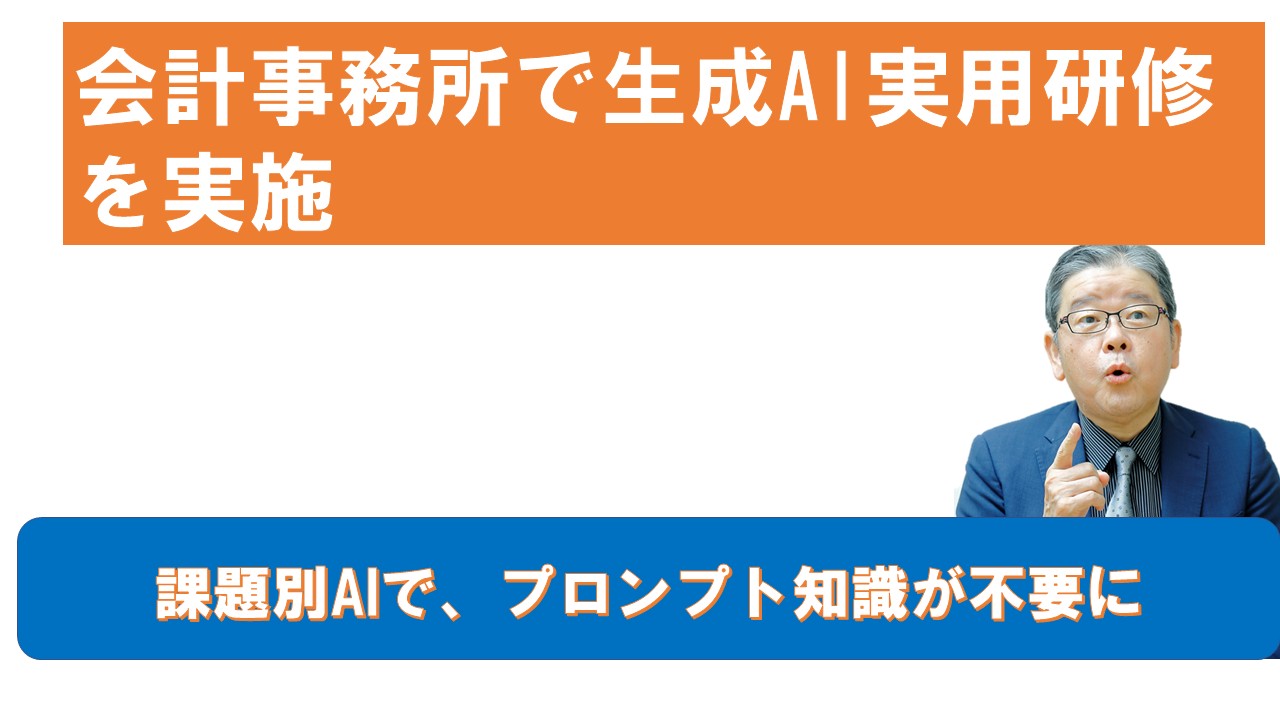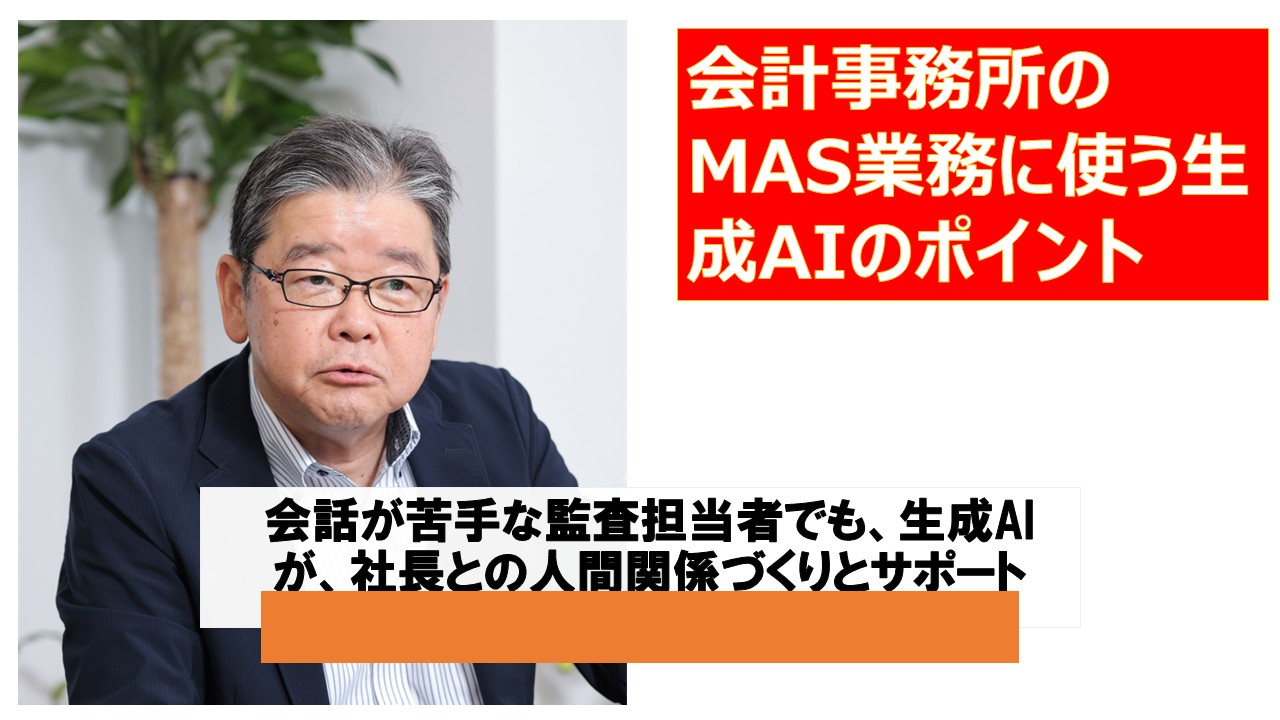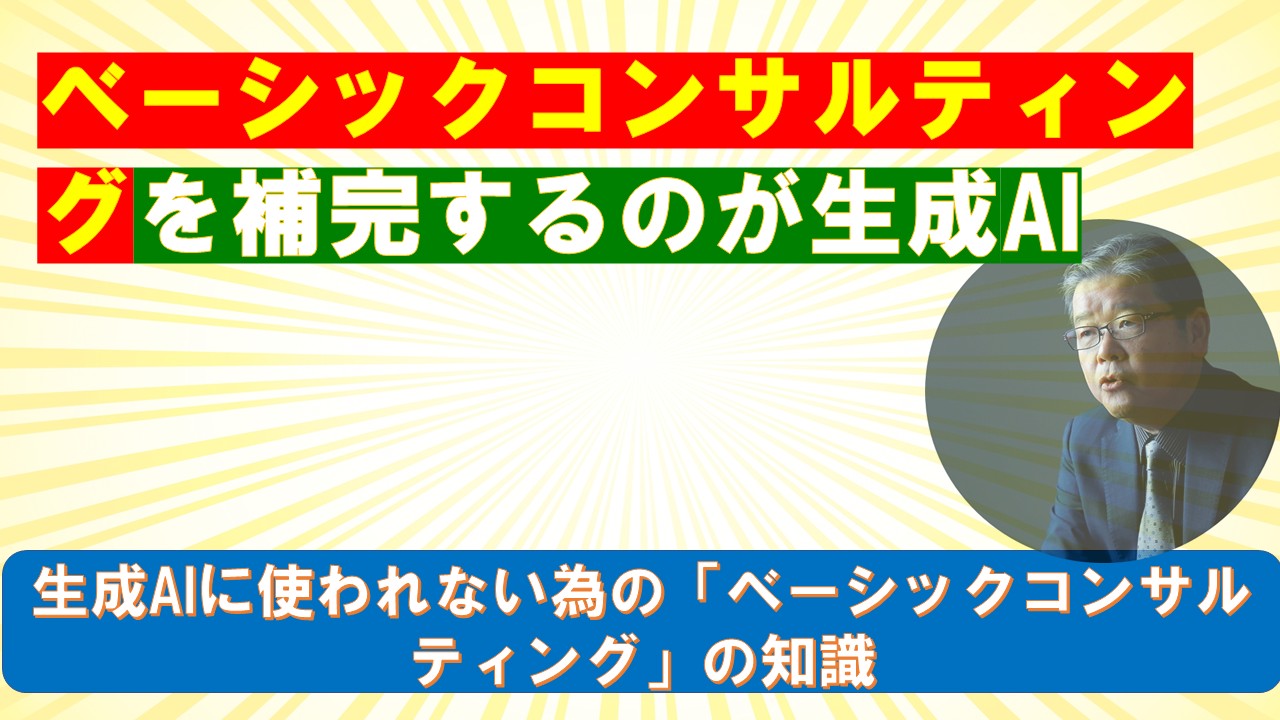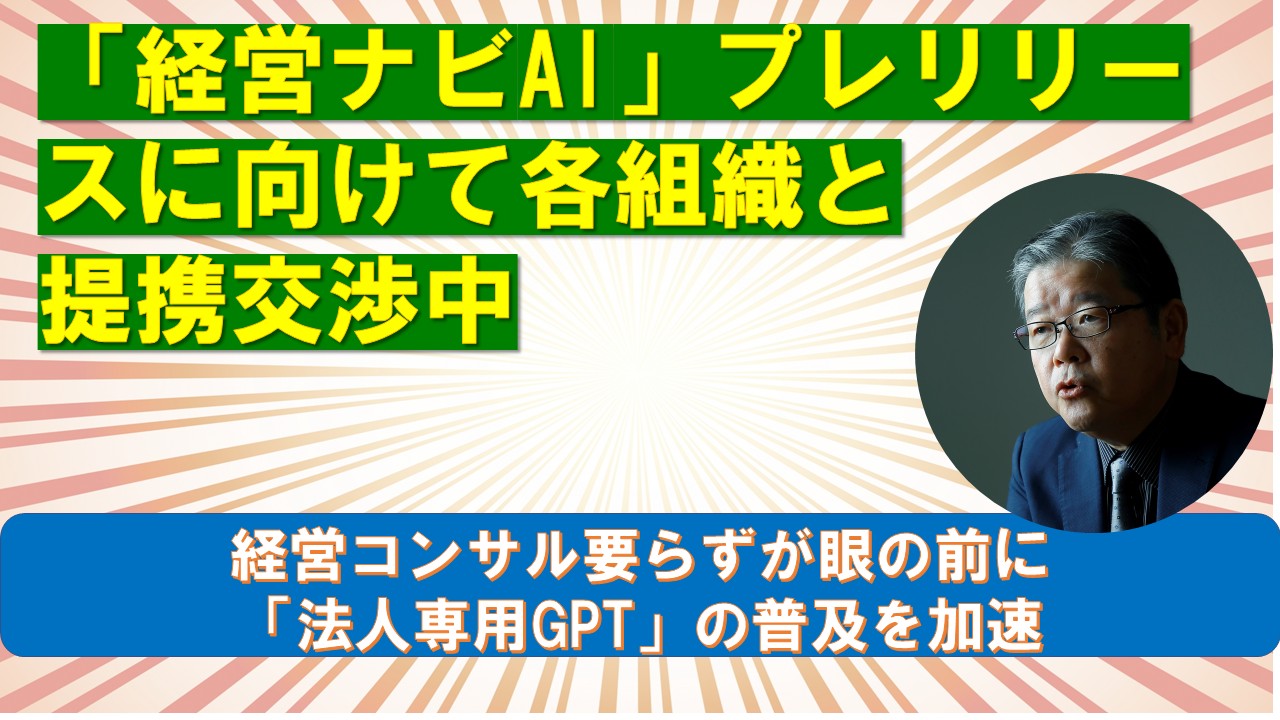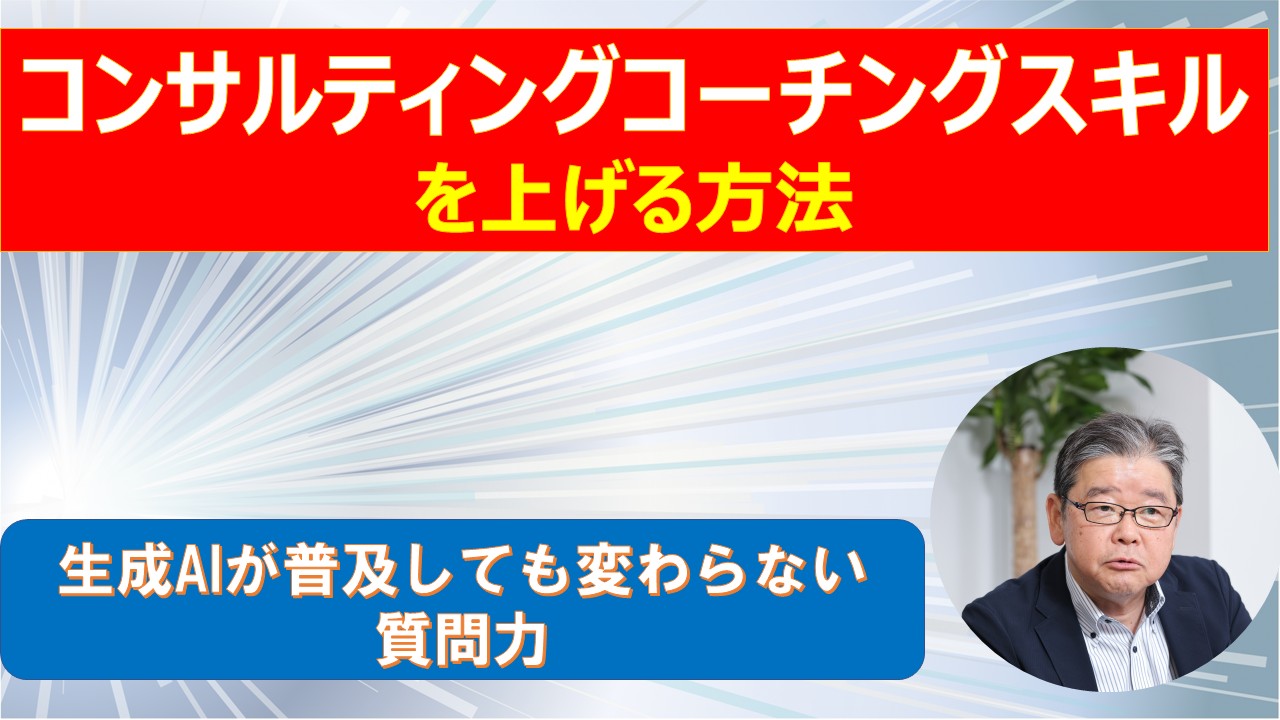![会計事務所のMAS業務に使う生成AIのポイント.jpg]()
![241225_ブログ用前置き.jpg]()
会計事務所職員のMAS業務への抵抗感について、このブログでも何回も取り上げています。
MAS業務の要諦は「監査担当者の経営者への深堀質問の有無」に尽きると思います。
先日も、ある税理士法人のコンサルティング部門の社長から、こんな話を聞きました。
「どんなに所長が『MASをやれ』とケツを叩いても、監査担当者はいろいろ理由をつけてやりません。
しかしとどのつまりは、顧問先経営者との経営の会話ができないから、苦手意識も相まって、面倒くさがって、やらないだけなんです」と。
そこで私が聞きました。
「じゃあ、もしその経営の会話で、質問すべきことをどんどん深堀していく会話を生成AIがサポートしたら、監査担当者はやりやすくなるよね?」と。
するとそのコンサルティング部門の社長は
「そうなんです。質問を一から自分で考え、ゴールの見えない会話は監査担当者は苦手です。しかし生成AIが、質問や会話をどんどん出してくれるなら、それに沿って経営者は答えてくれて、最終的なアウトプットがでる。それだったら、監査担当者も前向きになりますね」と。
そこから、今開発中の「法人向けGPT」である「経営ナビAI」の内容や機能の話をしました。
すると、そのコンサルティング部門の社長は
「嶋田先生、これなら監査担当者は考えることなく、生成AIから質問が来るので、それに答えるだけで、目的のアウトプットがでますね。このカテゴリーに会計事務所MAS業務専用のAIを組み入れたら、いいじゃないですか」と、興奮気味に話してくれました。
では、会計事務所のMAS業務を生成AIでどのように活用すべきでしょうか?