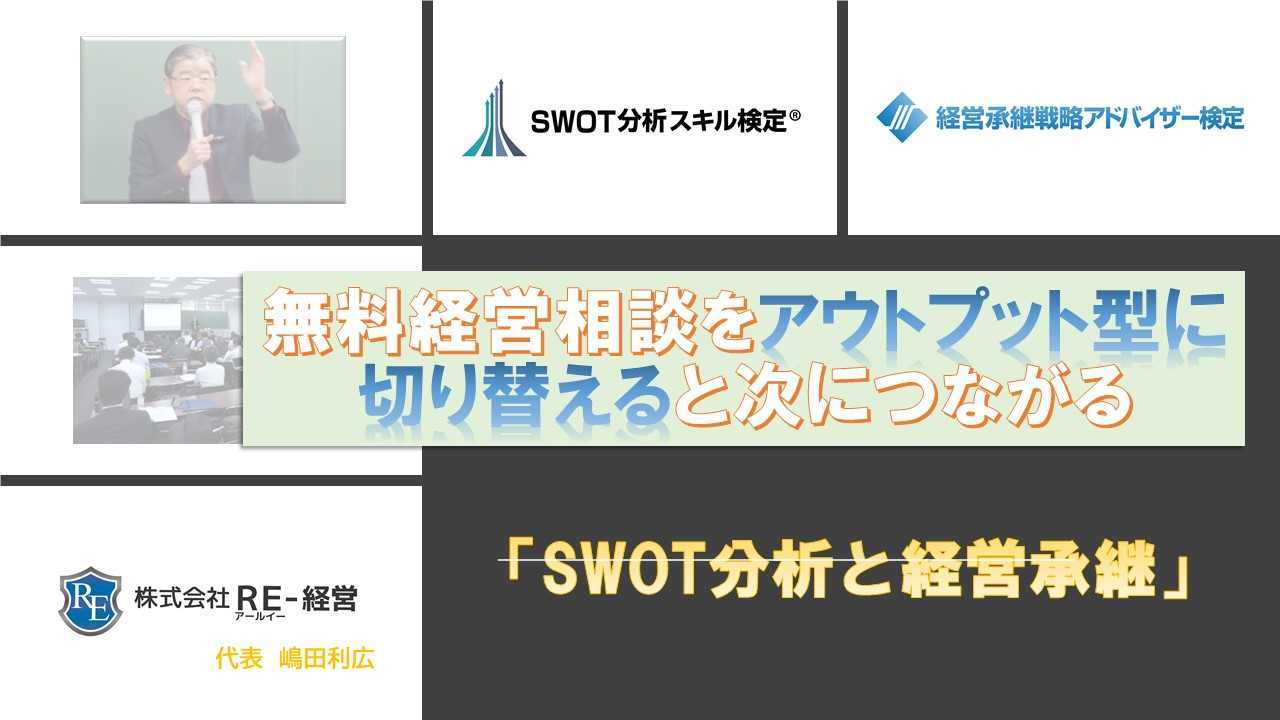
コンサルティングや研修の受注にはいろいろな動線があります。
知り合いからの紹介なら、その知り合いがもともと見込み客と信頼関係があるので、「面談⇒受注」とシンプルになります。
しかし全く一から見込み客と接する場合、
「SNS・FAX・DM」⇒「セミナー(オンライン・zoom)」⇒「無料経営相談」⇒「受注」
などのパターンが一般的です。
最近の傾向として、オンラインセミナーには参加しても、無料経営相談にまでいかないケースが増えている事も課題になっています。
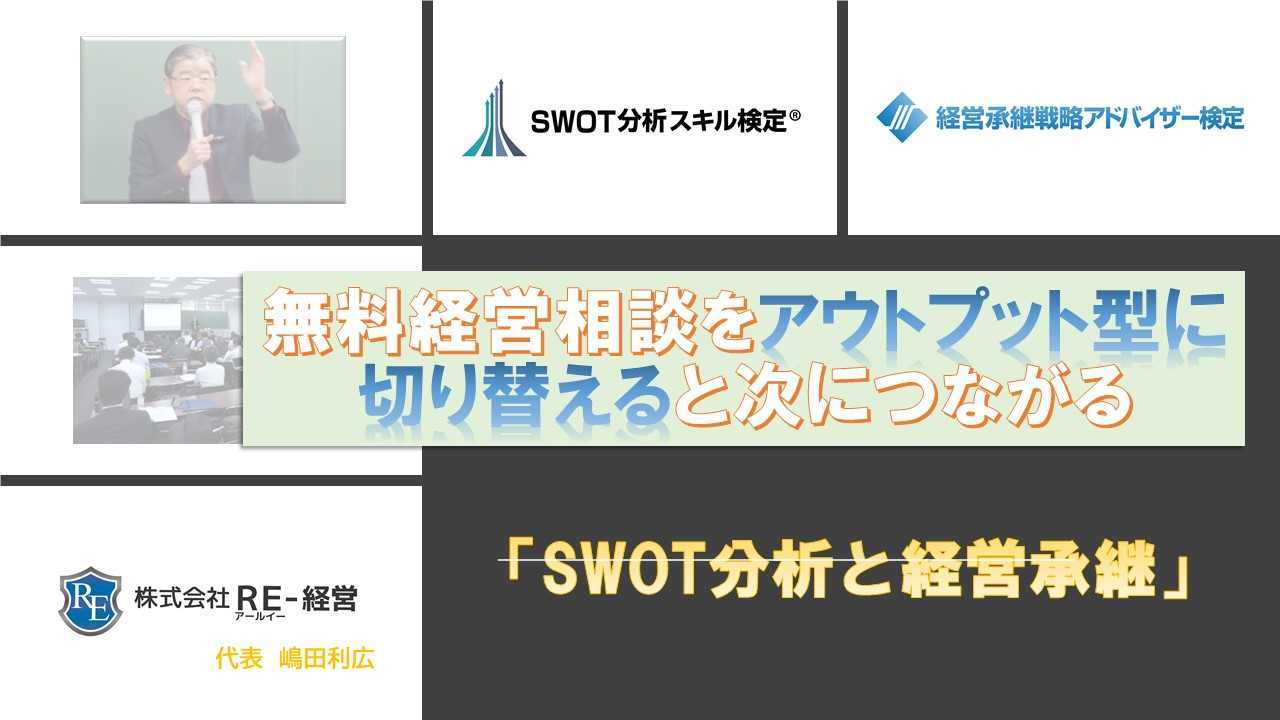
コンサルティングや研修の受注にはいろいろな動線があります。
知り合いからの紹介なら、その知り合いがもともと見込み客と信頼関係があるので、「面談⇒受注」とシンプルになります。
しかし全く一から見込み客と接する場合、
「SNS・FAX・DM」⇒「セミナー(オンライン・zoom)」⇒「無料経営相談」⇒「受注」
などのパターンが一般的です。
最近の傾向として、オンラインセミナーには参加しても、無料経営相談にまでいかないケースが増えている事も課題になっています。

後数日もすれば一生忘れられない2020年が終わります。
さて、2021年はどんな経営環境になるのでしょうか?
会計事務所のコンサルティングやその顧問先の中小企業の経営顧問をしていてつくづく思う事は、ありきたりですが「2021年はニューノーマルの中で、付加価値が最低条件」になるという事です。
特に対面型からリモートによる「非対面型」が普通になる昨今、これまでの面談の中での「会話からの付加価値」を見せにくい時代になりました。
「非対面型」はこれまでの面談型でのラポール(融和状態)や説得力を出した「提案」が分かりにくく、「眼で見えるカタチ」でしか反応しにくい側面があります。
そういう観点からも従来型の監査時に面談で行っていた事を違うスタンスで、付加価値を提供することが求められそうです。
コン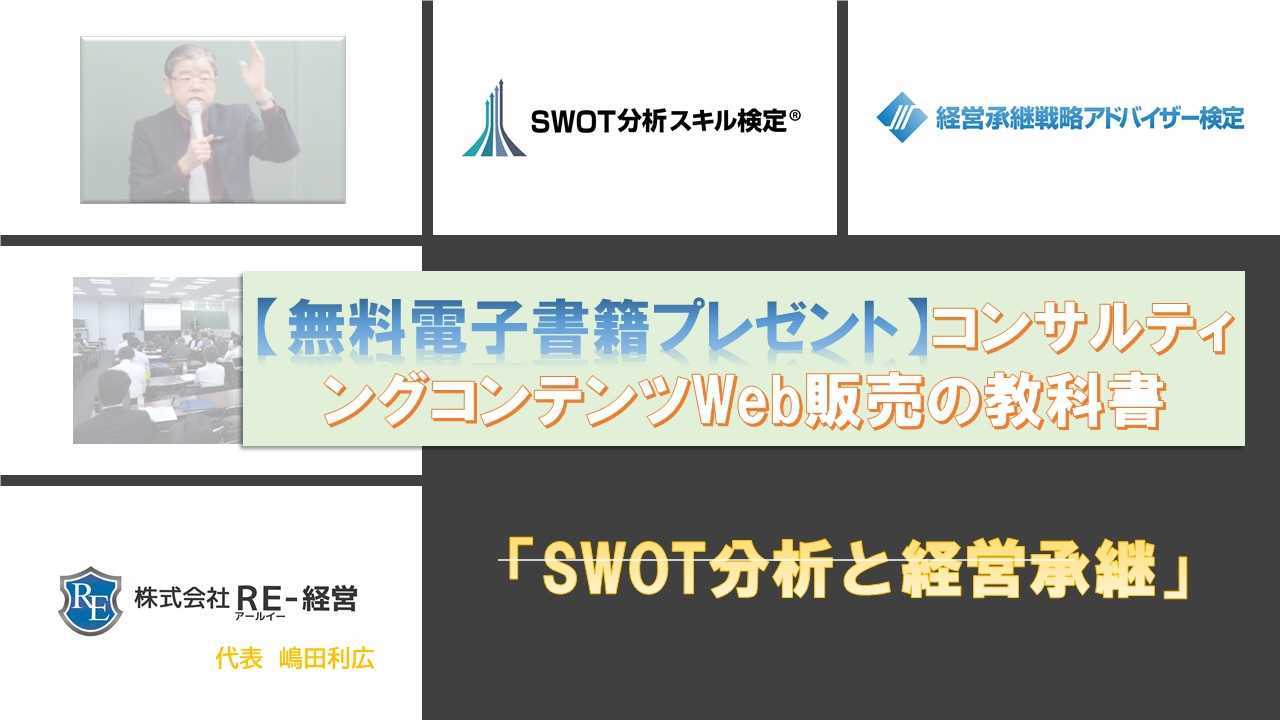 サルタント・研修セミナー講師の収入激減時代の第2の収益源
サルタント・研修セミナー講師の収入激減時代の第2の収益源
コンサルタントや研修講師の収入が激減した「コロナショック」。
後1~2年は対面型・集合型のコンサルティング売上は厳しい状況が続く事が予想されます。
その時新たな収益源として脚光を浴びているのが、これまで積み上げてきた「コンサルティングコンテンツ」をWeb販売するビジネスです。
大きな売上ではないが年間300~500万円の「非コンサルティング売上」があるだけでも、コンサルタント事務所経営は安定します。
そういう「コンサルティングコンテンツ販売」を目指す方向けに電子書籍としてマニュアル化しました。
これまで社外秘だった「コンサルティングコンテンツWeb販売」のノウハウを電子書籍で公開しています。
今回は無料ダウンロードされた方には、「コンサルティングコンテンツWeb販売 オンラインセミナー7講義」も無料視聴できるYouTube限定公開動画のURLが届けられます。
こちらから無料ダウンロードをしてください。
会計事務所の経営も今後は混迷をきたします。
コロナショックの影響が本格的に出てくるのが「コロナ融資の据置期間終了後」です。
資金繰りが厳しくなり、金融機関からの追加融資が受けられない中小零細企業が倒産、廃業を余儀なくされる可能性が高いからです。
そこで会計事務所経営は今後の事を見据え、今からいろいろな手を打つべき必要があります。
会計事務所の生き残り戦略の一つが「提案型アウトプット」を増やすことです。
そういう会計事務所を顧客にしている事業者(ITベンダー、ソフト企業、生保他)も、「会計事務所へ具体的な提案」をしていく事が求められます。
自社の商品を会計事務所に売ってもらう為だけのアプローチではなく、会計事務所の経営に役立つ情報提供や企画をする事です。
そうする事で、より高い信頼性や親密度が高まるわけです。
そこで、事業者主催で会計事務所の経営戦略セミナー(オンラインも含めて)を開催する事をご提案します。
既存の会計事務所だけでなく、新規の会計事務所開拓の接点開発にも効果があるセミナーを開催する事で、営業強化策にもつながります。
詳しくはこちらの動画をご覧ください。
講師依頼又はお問合せは、下記からお願いします。

コロナ禍で業績が急激に悪化した企業では株価が下がった事で、相続贈与を中心とした事業承継が進んでいます。
しかし、これら「財産相続承継」以上に重要な「非財産相続承継」の問題は遅々として進んでない所も多いようです。
「非財産相続承継」とは、
●経営承継後の経営戦略
●役員幹部定年以降の組織・人事体制
●会長から社長への実質的な職務権限移譲計画
●後継者時代の役員幹部の職務責任とコミットメント
●経営理念、価値観、経営判断基準の承継
こういうものを「非財産相続承継」と我々は読んでいます。
それらを「見える化」することを「経営承継の可視化」と定義しています。
今回無料電子書籍で紹介する5つの経営承継失敗のケーススタディは、この「非財産相続承継」が上手くいかなかった事に起因しています。
そしてこの5つの事例はどこにでもある「中小企業・同族企業のあるある」なのです。
この無料電子書籍はドキュメントの物語スタイルで簡潔に読む事ができます。
5つのケーススタディを予備知識として頭に入れることで、これから起こる後継者との問題に事前準備ができるのではないかと思います。
あるコンサルタントの方から質問が来ました。
「今回のコロナ禍で収入が落ちたのはある意味仕方ないと割り切っています。ただ2021年もこれが継続すると大変厳しい状況になります。
「非コンサルティング売上」の必要性は感じていますが、どのように販売し、またどう実際のコンサルティング受注に活かすかイメージができません・・・・」
と。
コンサルタントや経営支援をしてきた人には何らかのコンテンツがあるものです。
今のwithコロナの時代では、対面型のコンサルティングは大きく制限され、それに伴いコンサルティング売上や研修セミナー売上が激減し、2021年に向けて「事業計画」をどう組むか、悩ましい方もいると思います。
もし、「コンサルティング・セミナー・研修売上」以外に、「非コンサルティング売上」であるコンサルティングコンテンツをWeb販売できれば、「コンサルティグ収入減少分を少しでも補填」ができます。
この「コンサルティグコンテンツ」をどのようにWeb販売できるように商品化するのか?
コンサルタント経験の中からデータやテンプレート、実例マニュアル類は持っていても、その販売までに流れや段取りをご存じない方がいます。
それは「宝の持ち腐れ」です。
また、「こんなの売れないよ」と最初から「コンテンツWeb販売」を考えようとしない方もいます。
内容が薄く、ネットで無料で直ぐに手に入るものなら「コンテンツWeb販売」は成立しませんが、ちょっと専門的で、それを求める人は少数だが、欲しい人はおカネを出しても欲しいコンテンツもあります。
前述の方の質問にもありましたが、コンサルティングコンテンツはWeb販売だけでなく、見込み客へのアプローチに使えるので、コンサルティング受注にも直結します。
どういう事か?
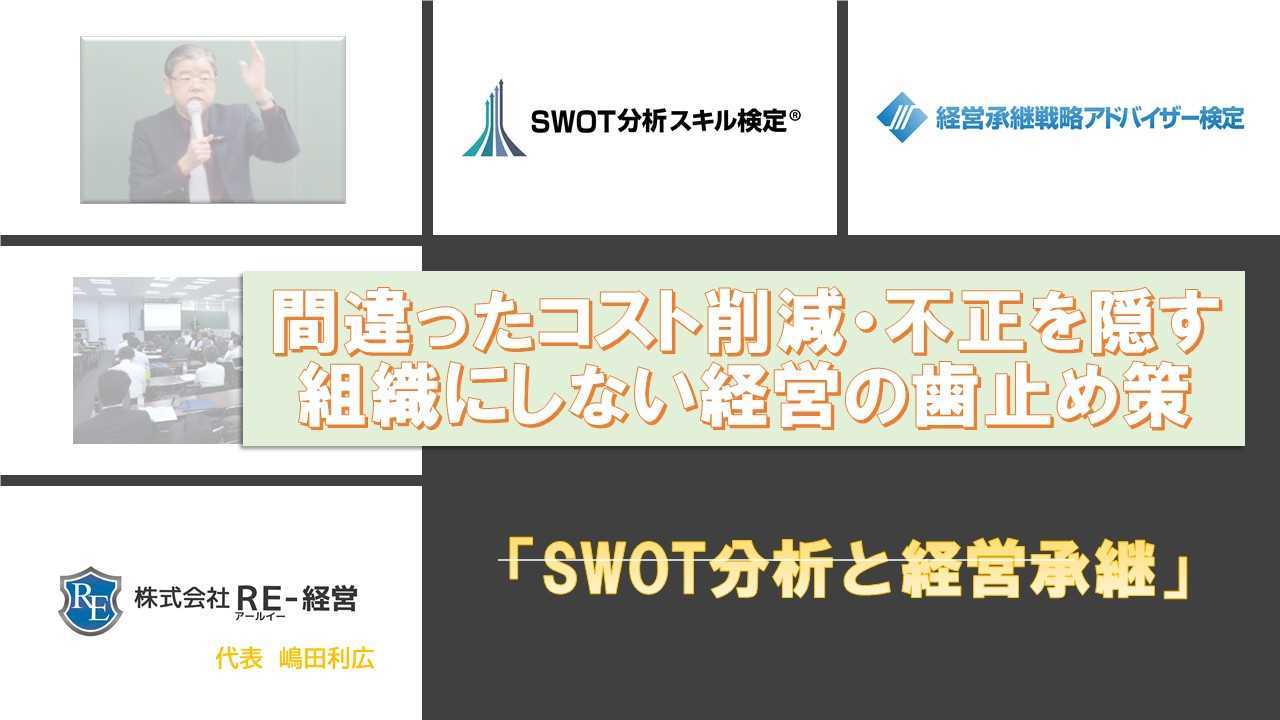
今回のコロナ不況で業績が低迷すると、多くの企業はコスト削減に走ります。
適切な範囲のムダ削減なら構いませんが、目先のコストの為に品質に影響する部材や仕組みにまで手を付ける企業が増えてきます。
しかも経営者の知らないところで。
これまで製造業・建設業の経営顧問の経験が多いので、こういう課題が発生しないように常々経営者と協議してきました。
しかし、昨今の重要部品の強度不足のデータ改ざんや品質偽装によるマンションの傾き等、本来はあってはならない事が起こっているのです。
今、特に注意しないといけないのは、コロナ不況でいたるところでコスト削減が進むうちに「確かな品質維持で長期の信頼作りよりも、短期のコスト削減で将来に禍根を残す品質問題」が水面下で起こる可能性が高い事です。
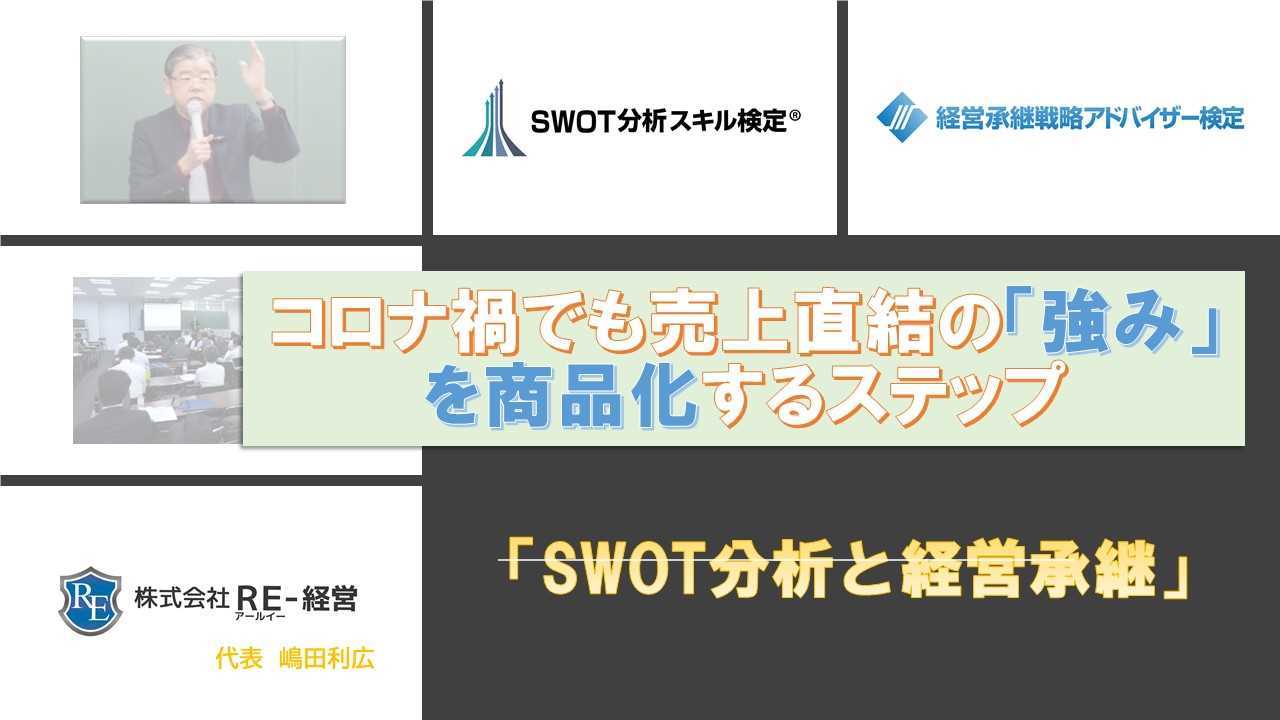
「強みは細部に宿る」と前回のブログで書きました。
「強み」を小さく見る事で、それを必要としているターゲット顧客を発見しビジネスを展開していく、という感じです。
そこで問題になるのが「強み」は分かったが、それをどう収益につなげるかという事です。
一般に「強み」が分かっても、それは一部の差別化の範囲で少しだけ他社より、サービス面で優位に立っている程度です。
だから「強み」が自己満足の域を出ない訳です。
「強み」が自己満足の域を出ない場合、それは「良い点」に格下げになる事を意味します。
「強み」を収益化する事をどう展開していくか、我々のSWOT分析ではそこに注力します。
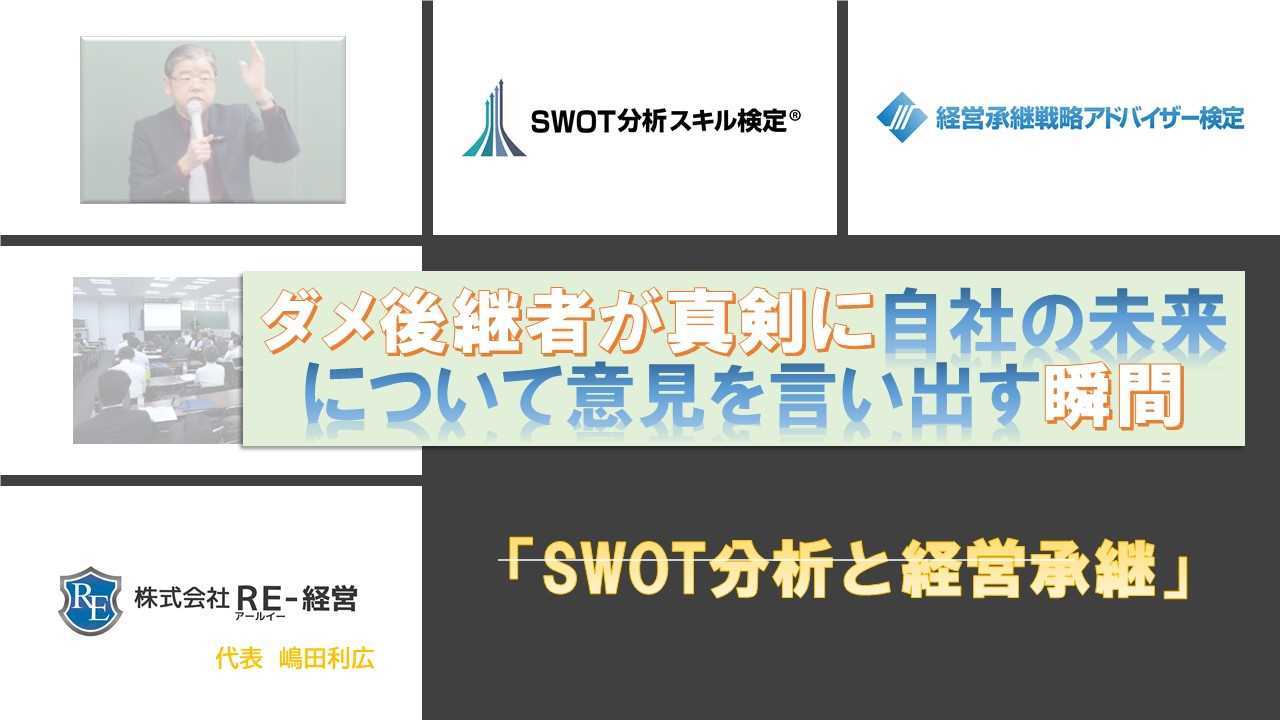
後継者教育にはいろいろなパターンがあります。
これまでも各種の後継者研修があるし、セミナーもあります。
ところが後継者の既に真剣に経営承継を考えている方と、まだまだ若くピント来てない方、そして経営承継を考えるべき年齢なのにまだまだ自発性がない、依存・責任転嫁体質の方…
経営者にとって、3番目の「ダメ後継者パターン」は頭を悩ますところです。
これは甘やかして育ててきたのか、もともとビジネスセンスや資質がないのか、理由はさておいて、こういう後継者が後を継ぐと困るのは従業員や顧客、取引先です。
ところが、そんな一般的にはダメ後継者でも意識が変わる瞬間というものがあります。
今回はそのドキュメントを紹介しましょう。
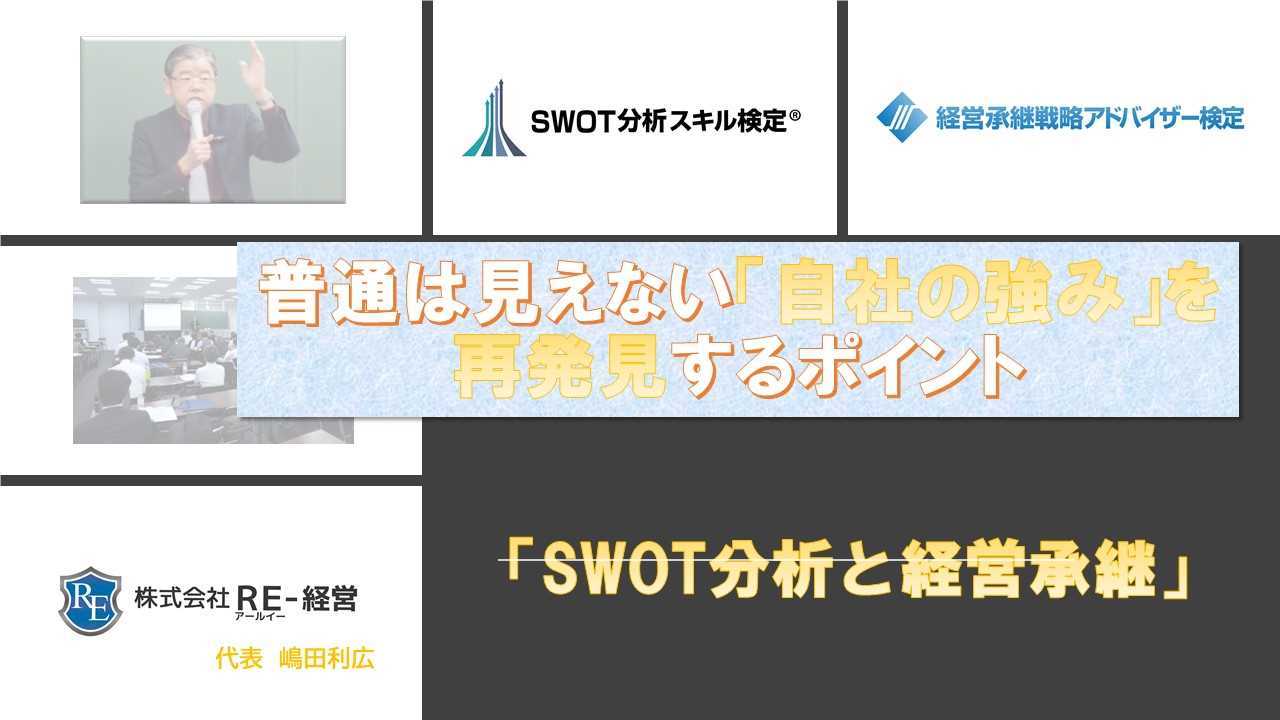
今後、確実に「特徴のない企業」は淘汰されます。
こんなことは多くの経営者も総論としては理解しているはずです。
では、本当に「自社の特徴づくり」に努力をしているのか、と聞けば?の経営者も多いですね。
「自社の特徴」と言っても分からなければ「自社の強み」に置き換えても良いです。
アフターコロナ時代やこれからの「低温経済」で生き残るには、「自社の強み」を極大化して「攻めの経営」に邁進するしかありません。
では、「自社の強み」をどうやって紐解けばいいのか?
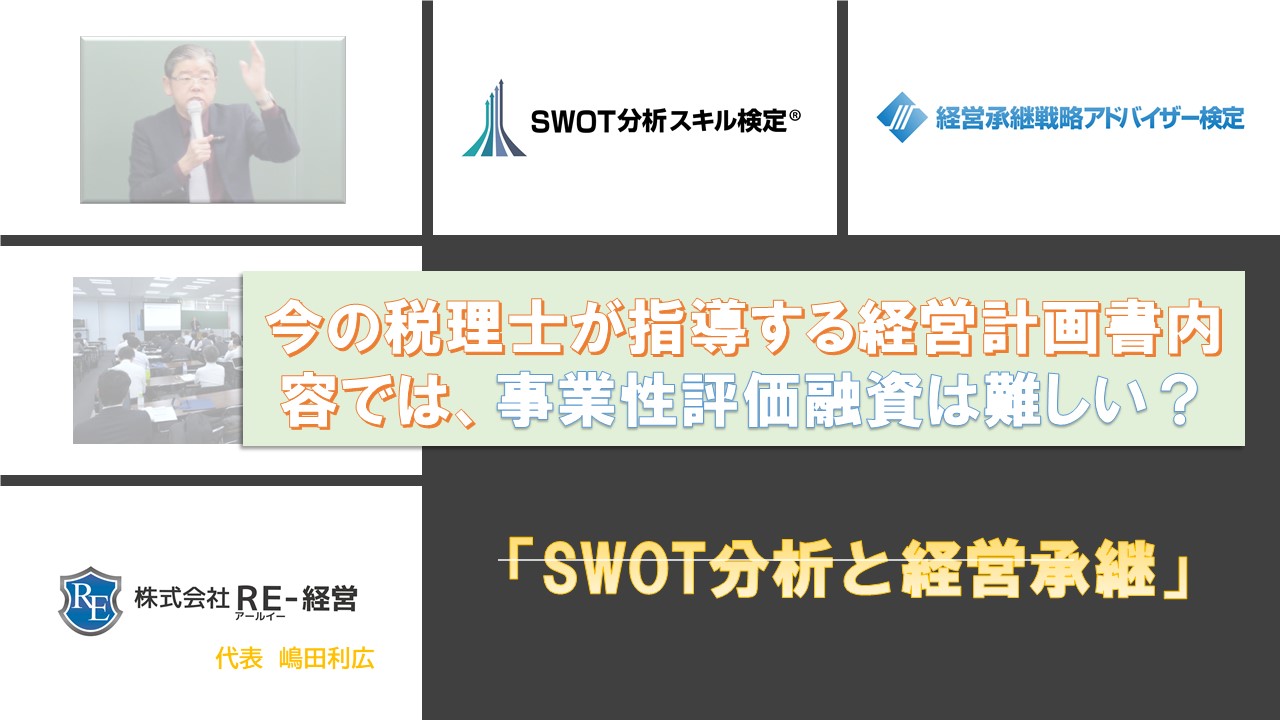
知り合いのコンサルタントから最近聞いた話です。
ある地銀の融資担当を話す機会があったそうです。
その担当から税理士事務所が指導している経営計画書では、今後の融資は難しいという話です。
どんな内容だったか?
その担当者が言うには、
「返済をする為にはいくらの収支改善が必要かは細かく数字になり、キャッシュフローまで出ています。
しかし、肝心要の具体策が役員報酬減額を含めたコスト削減や、抽象的な商品戦略、顧客戦略ばかり。
多分経営者が言った言葉をそのまま掲載しただけでしょう。根拠を感じない。
これでは、その経営計画書の信ぴょう性が疑わしいし、何より経営改善するとは思えない。」
だそうです。
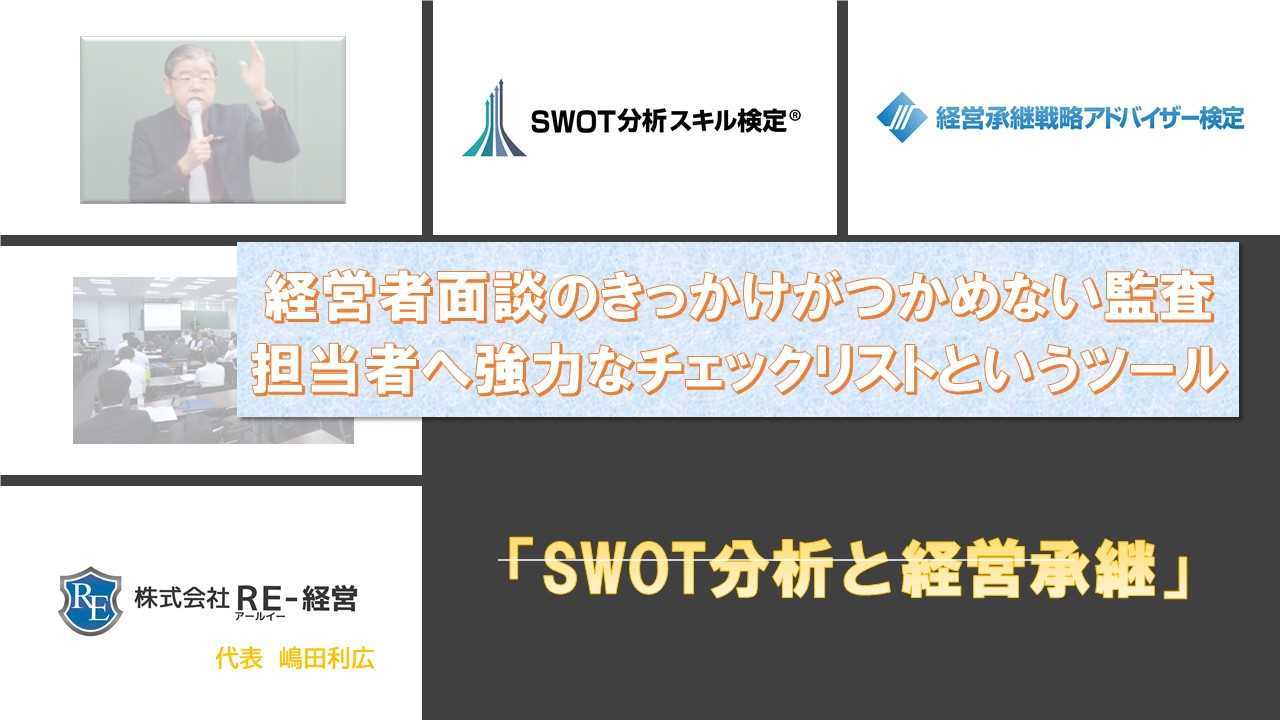
以前もこのブログで、経営者面談ができない、コミュニケーション能力不足の監査担当者が「社長面談が増えた理由」として紹介しました。
その心は「定期的にチェックリスト」を持参して、それを説明する所から始めたという事でした。
その後、これを全員に展開していますが、確実に経営者からの反応が出ています。
実際どのように全員展開しているのか、その進め方を紹介しましょう。
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。

