2025.9.8 生成AI勉強会受注から経営顧問へのマネタイズ
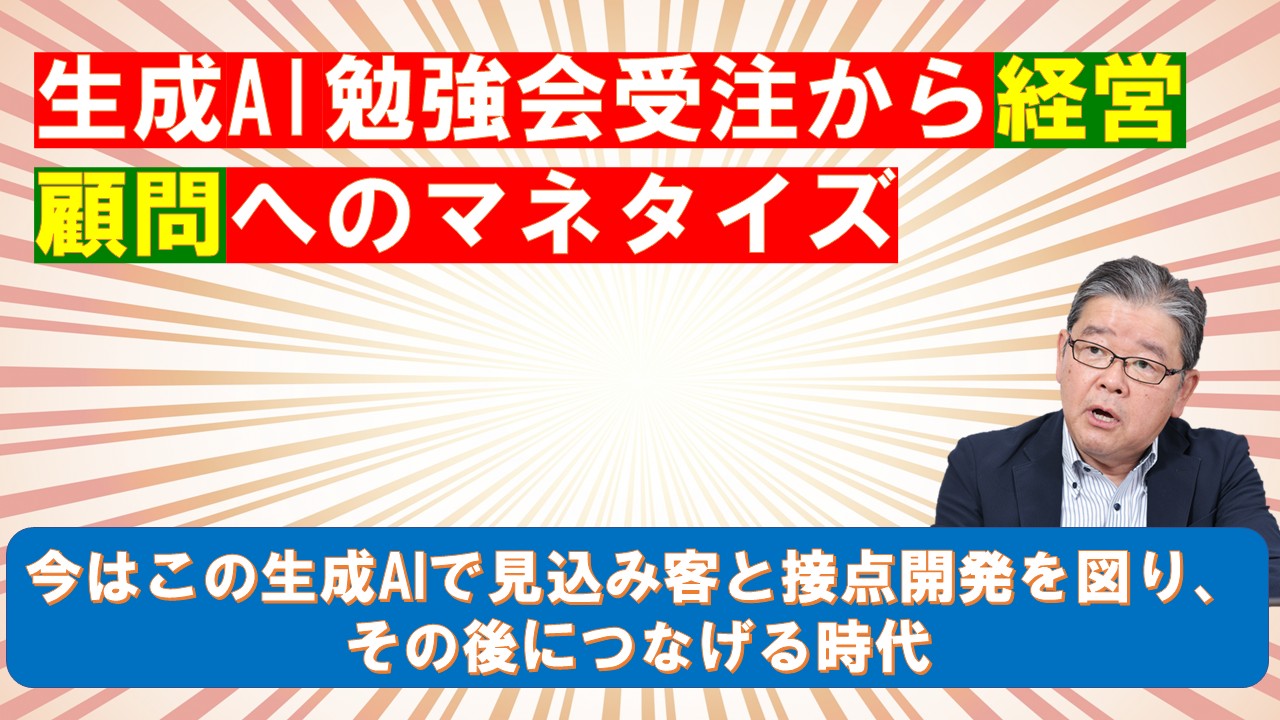

コンサルティングプロンプト研修会でもいろいろな「コンサルティングプロンプト」とその生成物も公開しています。
ここまで生成AIでコンサルティングの成果物の第1次素案が簡単にできてくると、コンサルタントのマネタイズはどんどん変わってきます。
ただこういうプロンプト技術を学習したり、精度向上を図っているのはまだまだごく一部で、多くの中小零細企業はプロンプトの「プ」の字もよくわかっていません。
経営者の「生成AI活用ニーズ」は高いのですが、問題は「生成AIを何からどう導入すればいいか分からない」という事です。
ChatGPTやGeminiの無料版は個人で使っているものの、個人任せではセキュリティも心配だし、全員に有料版を使わせるとコストもバカ高くなります。
実はそこにコンサルタント業界の新たなマネタイズがあるのです。
コンサルタントは基本的な生成AIの知識と活用スキルさえあれば、そこに新たなコンサルティング受注が生まれるという事です。
では実際にどうすべきか?
1,生成AIと活用勉強会を提案
先ず、コンサルタントや士業が講師となり、生成AIの基礎的な学習をしてもらい生成AIに興味を持つことが大前提です。
興味さえあれば、どんどん知識は入ってきます。
私自身も2024年8月に「これば生成AIを真剣に学習しないとやばい」という危機感から、ある生成AIのオンラインセミナーに参加。
その後、セミナーで学んだプロンプトの基本公式を自分のコンサルティングのアウトプットに当てはめて、トライ&エラーを繰り返しました。
そこから3か月で、「チェーンプロンプト」でこれまで私自身が実践してきた多くのコンサルティングの素案ができる事を体感しました。
そのあたりから、関係先の企業や会計事務所の「生成AIの基礎勉強会」の提案実施をしてきました。
その結果、複数の会計事務所では「生成AI継栄塾」を開催をして、更に講演会やセミナーの機会も増えました。
そして、その講演会やセミナーに来た中小零細企業の経営者が「自社で社員向けに生成AI勉強会をしてほしい」と書くようにアンケートを準備します。
すると、複数の企業がその項目に〇をつけるので、後はアポをとって社内生成AI勉強会を行うだけです。
つまり「生成AIの社内勉強会」のニーズが高いという事です。
この後のバックエンドを考えると、この「生成AI社内勉強会」は低価格でも受注しましょう。
2,取り合えず「生成AI導入6か月プロジェクト」を提案
単発の「生成AI活用社内勉強会」を実施した時に必ずアンケートを取ります。
そのアンケートには「今後生成AIをどう使いたいか」「今日のカリキュラム以外に生成AIについてどんな事が知りたいか」「実際の業務にどう生かしたいか」などの質問を入れて、記入後提出してもらい回収します。
そのアンケート結果を勉強会後に経営者と確認して、「社長、取り合えず6か月位の生成AI導入プロジェクトをしましょう。プログラムと費用を書いた企画書を出します。」と言ってアポをとります。
一度生成AIの勉強会をした経営者としては、それだけでは何も前に進まない事は分かっています。
そこで、実際に生成AIプロジェクトをコンサルタント主導で進めてもらう事は快諾しやすくなります。
更に6か月間という限定なので、費用もそこまで心配いりません。
この6か月間企画書は生成AIで書かせることもできますが、この6か月間は次の経営顧問受注の為の布石でもあるので、次につながる要素を各カリキュラムに入れる必要があります。
6か月間スケジュールの考え方は
1か月目・・生成AIを知る(生成AIの設定、特性や生成されるテキスト、画像、動画、音楽)
2か月目・・生成AIを使う(単発プロンプトの出し方、チェーンプロンプトの出し方、追加指示の仕方)
3か月目・・業務効率化の課題整理とと生成AIでできるプロンプト開発(MyGPTs経験)
4か月目・・各部門の課題AIのプロンプト開発と成果事例報告と検証
5か月目・・生成AIで業務マニュアル、引継ぎパターン、職務基準、求人票作成
6か月目・・カスタムChat(MyGPTs)の設計と検証
私の場合は「各部門の業務効率化」「業務標準化のパターン化」「キャリアパス」「スキルマップ」などの社員の未来に関わるテーマを6か月プログラムに入れて、そういう未来を実現するには、ビジョンづくり、経営計画書作成、SWOT分析分析などの得意分野に誘導する内容をちりばめます。
ただここで問題があります。
その企業の参加者に生成AI無料版を使って、いろいろ生成経験をしてもらうと、すぐにトークンオーバーになり、数時間待たなければなりません。
せっかく気持ちが乗ってきたのに、冷や水を浴びせられるのです。
だからと言って、有料版に参加者全員が入るのはコスト面でも管理面でも問題があります。
もし可能なら事前に弊社の「経営ナビAI」のテナントのなってもらえれば、セキュリティの心配なく生成AIが使えます。
3, プロジェクト中に「経営計画」「人事評価」に介入
6か月間で生成AIの活用の仕方が分かっただけでなく、経営判断に使えるようにします。
生成AIプロジェクト中に感じた事、メンバーからの相談内容が経営計画、ビジョン、人事評価に関連した情報を収集しておきます。
そして、その課題整理と解決の為に何がどう必要かを経営者と個別に面談します。
この6か月間の動きの中で「経営計画と「人事評価」に介入できる情報を意図的に集めます。
途中経過として3か月過ぎ当たりで経営者の「進捗報告と今後の課題」を提案する中に、経営計画と人事評価の必要性を記載します。
この時は受注まで行わず、その必要性の訴求だけで結構です。
ただ5か月目が終わる頃に再度、経営者面談を行い、経営計画と人事評価に関する今後のコンサルティング計画書を出します。
事前に根回しと匂わせをしているので、決して唐突感はありません。
そこで延長契約に進めます。
4,その後1年間の経営顧問契約に更新
6か月プログラムの終了と同時に、コンサルティング計画書に沿って、1年間の経営顧問契約をします。
経営顧問契約で大事なのは最初の1年です。
この1年間に「コンサルに費用を払ってでも導入してよかった」と思わせなければなりません。
その為には、前述の「経営計画書作成」と「人事介入」は不可欠。
もし決算月が近いならそのまま「年度経営計画書作成」の作業に入ります。
また決算月が過ぎてしまってなら、中期ビジョンづくりに入ります。
また人事介入は「経営計画書や中期ビジョン」の中で、人事評価制度や採用サイトコンテンツコンサルティング、KPI設定、生成AI導入計画を入れる事で、介入しやすくなります。
特に経営計画書作成では「部門方針や部門計画」を作成するので、その時に幹部との個別面談をして、幹部のレベルや意識を把握します。
それぞれの幹部に対してのコンサルとしての見解を適宜、経営者に伝える事で、「幹部人事の黒子役」を目指します。
そういう事を最初の1年間で行い、毎月確実の経営者との個別面談で内容確認をしていれば、2年目も3年も基本的には継続します。
ここで必ず、毎月1回は経営会議の前後の「経営者面談」は必須です。これをしないと意外に短期間で解約されやすいので注意しましょう。
こうやって「生成AI勉強会」」から経営顧問につなげていくことが、ここ最近では良いアプローチではないかと思います。
この生成AI勉強会も経営ナビAIを使う事で、進めやすくなります。この仕方も随時開催している「経営ナビAI無料オンライン説明会」でお話しているので、「経営ナビAI」にご興味のある方は是非ご参加ください。
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。








