2025.4.23 商材根拠のある経営計画書の作成支援に欠かせないポイント
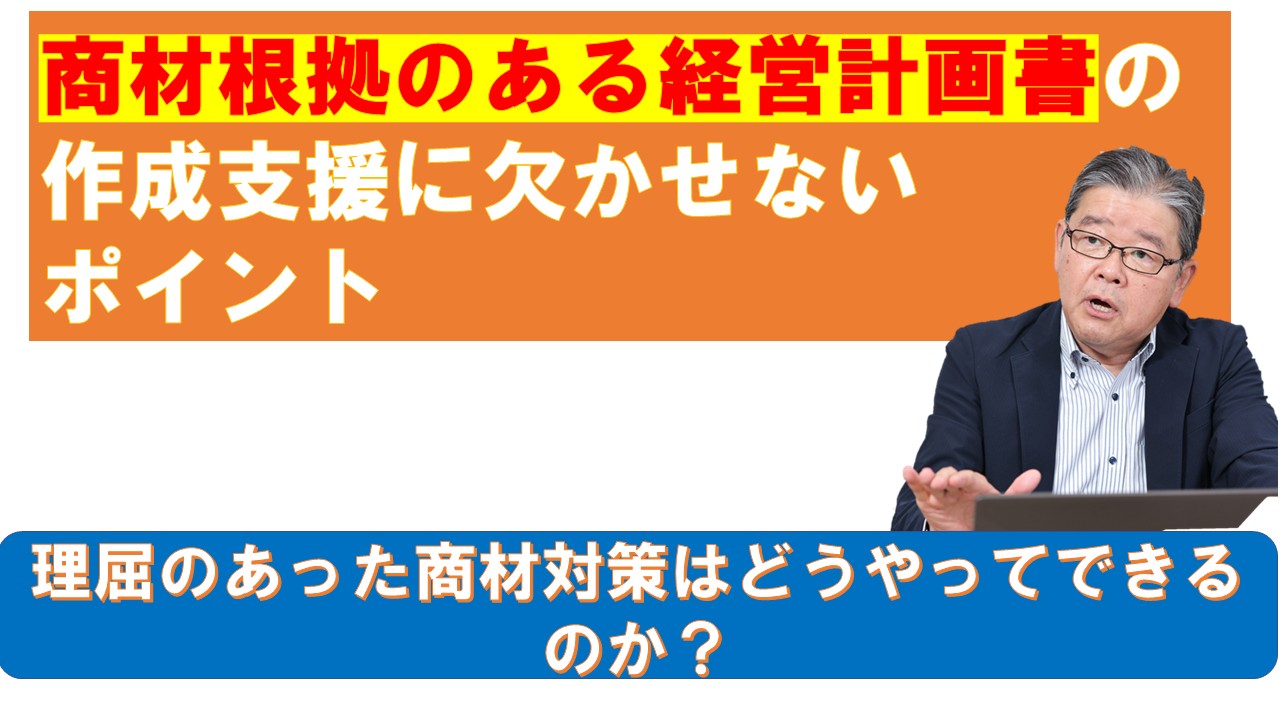

先日はコンサルや会計事務所のコンサルノウハウのサブスク塾である「RE嶋田塾」で、「商材根拠ある経営計画書作成支援ノウハウ」を講義しました。
これまでも「根拠ある経営計画書」についてはたくさんセミナーしてきたし、それに関する書籍やこのブログも書いています。
「商材根拠のある経営計画書」とは何なのか?
また、これを経営者からヒアリングしながら誘導するスキルってどういうものか?
について改めて考察する機会になりました。
最近は「KPI監査をベースにしたSWOT分析からの経営計画書」を中心に展開していますが、もともとの原点を整理することができました。
1,危機感が生まれる「破局のシナリオ」分析
「破局のシナリオ」とは、「今のまま、通常の努力を継続した場合、各商材の売上や原価、固定費がどう変わるのか」を整理します。
この「破局のシナリオ」という言葉は、刺激的な言葉ですが、経営者に問題意識を持ってもらうには、ぴったりな言葉だと思います。
「破局のシナリオ」を考えるときの条件は
⑴ここ5か年の加重平均の%で、各商材や顧客別売上を今後の予定に入れる
⑵これまでもいろいろな努力をしてきて、今の結果だから「既存商材」では特別な要素が
ない限り売上計画を増やさない
⑶原価や商品仕入れは昨今のインフレや円安が続くと想定して「悪い予想」をベースにする
⑷人件費(労務費含む)は、賃上げを入れた多めの経費にする
(そうしないと退職者が増え、さらに売上ダウンになりかねない)
⑸償却費や修繕費、その他の経費でも「やらないと大変なことになる」投資は計算に入れる
こういう条件を入れていくと、当然「売上ダウン、粗利ダウン、固定費アップ」になり、今が赤字なら、さらに赤字が拡大する。
それが「破局のシナリオ」です。
この「破局のシナリオ」のExcel計算書を見ると、経営者から「こんなに悪くなるはずがない。
いざとなったら人件費も修繕費も経費も減らすしかないから」と。
しかし、それはリストラ的発想で、「企業が縮小し、課題がどんどん山積している状態で赤信号」になっている状況を作り出します。
取り敢えず、経営者にはこの現実を受け止めてもらいます。
2,融資返済や成長投資に必要な利益から逆算
借入返済をしていくにはキャッシュフローが必要です。
そのためには必要な営業利益があるはずです。(営業外収支にマイナスが大きい場合は経常利益で計算)
そこから「必要固定費」や「最低必要な投資(給与や設備、修繕、広告)」を入れた販管費を作ります。
その販管費はおそらく、昨年対比でかなり上昇しているはずです。
また、原価では商品市況や外注費の値上げ、労務費アップも考慮して原価率を出します。
すると、「最低必要営業利益」+「必要販管費」+「必要原価」=「必要売上」となります。
そして「必要売上」ー「昨年の売上」=「差額商材売上」として、認識します。
3,必要売上になる商材をクロスSWOT分析でねん出
差額商材売上が分かったら、それを念頭に置いてクロスSWOT分析の「積極戦略」は商材別の対策を出します。
ここでは3カ年で業績改善を図る為「改善戦略」も重要になります。
「積極戦略」では、新戦略の商材(新商品、新企画、新販促など)や新戦略の顧客対策(クロスセル、アップセル、顧客開拓、チャネル開拓など)が打ち出されます。
しかも、その各新戦略には「単価」 「販売個数」 「平均粗利」、そしてその新戦略実施に必要な経費支出も「積極戦略」シートには書かれます。
差額売上を見ながら、新商材対策がどこまで近づけられるかがポイントです。
しかし、現実的に「差額売上を埋めるほどの新戦略商材のバリエーションがある」企業は少数派。
やはり、どこかの段階で既存商材の「売価アップ」 「粗利改善」の対策も入れざるを得ません。
本気で商材対策を狙う「積極戦略」をしない限り、空論になるのです。
最近では、新商材アイデアが埋まらない場合、生成AIに諸条件を入れて「積極戦略アイデア」を詳細に出させることも増えてきました。
4,既存戦略と新戦略で整理された中期収支計画作成
さて「「積極戦略」で新商材や既存商材の値上げ、粗利改善などが詳細に議論され、必要なワードがフレームに記載されています。
それを受けて「具体策連動の中期収支3カ年計画」を作成します。
ここでは
●既存商材の破局のシナリオでの予測
●既存商材の売価アップや粗利改善の対策結果
●新商材の業績貢献結果
を分けて整理します。
また原価や固定費は、破局のシナリオで予測したものをベースに調整します。
そして、ここで何回かシミュレーションが必要です。
最終の営業利益や経常利益は譲れない金額なので変更しませんが、その上の販管費や原価、売上は調整しながら最終金額を設定します。
もし、「売上アップが少なく、粗利改善の比重が大きい」場合、その粗利改善の対策案や機械投資が入っていないと理屈が合いません。
また「売価アップ」だけが大きい場合、それにふさわしいサービスにも経費が掛かるはずです。
そうやって、当初のSWOT分析での商材や対策以外の調整対策がここで出てくるのです。
そこで新たに発生した対策案を、再度「積極戦略」の欄に追記します。
またこの「具体策連動の中期収支3カ年計画」は左側の「損益計算」、右に「その根拠対策と金額」が書かれているので、分かりやすいのが特徴です。
5,中期ロードマップの作成
取りあえず「3カ年の収支計画」と「積極戦略」からの新戦略具体策が決まったら、その年度導入にふさわしい中期のロードマップ(工程表)を作成します。
当然ですが、赤字幅が大きい企業がいきなり黒字にする計画には無理があります。
無理な計画は初年度に「何でもかんでもぶち込んだ計画」にしがちで、結局実行できず、金融機関から信頼をなくします。
だから初年度は赤字幅が拡がり、2年目は赤字が縮小、3年目にトントン、4年目から利益が出て、5年目に返済原資が出せる利益という計算になります。
しかし、この時間軸だと金融機関が認めてくれない。
そこで3年目から利益が出るような対策に変えていく必要があります。
そのためには初年度の成長投資以外の経費削減は必須になります。
そして、実行具体策も初年度に集中するしかありません。
言い訳ではないですが、経営改善計画書を出した銀行とのバンクミーティングを想定して、収支結果だけでなく、「KPI設定」を行っておくことも必要です。
収支が予定通り行かない場合が多い昨今、それでもKPIは予定通り進んでいるから「経営者は本気で経営改善の努力をしている」とアピールできるからです。
6,単年度アクションプラン作成
中期ロードマップを、より初年度のアクションプランとして具体化します。
最近は「KPI監査モニタリングシート」でアクションプランを作成して、PDCAを回すことが多いので、アクションプラン単体を作成することは減りました。
それでも、決めた行動計画を確実にチェックしていくためにもこのアクションプランは必要です。
このアクションプランのPDCAやKPI監査モニタリングを行う支援は、「業績検討会議」に我々コンサルタントが参加して議論や記録をリードしていきます。
トランプ関税の影響で、国内の中小企業にも不況倒産や資金繰りが悪化する中小企業が増えています。
これからますます「根拠ある経営改善計画書」の必要性が高まることでしょう。
YouTubeでもこの「根拠ある経営計画書の流れ」は解説しています。
【SWOT分析を活用した根拠ある経営改善計画書」の作成の仕方】
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。








