2025.4.16 主要人材が辞めた時の業務の見直しロジック
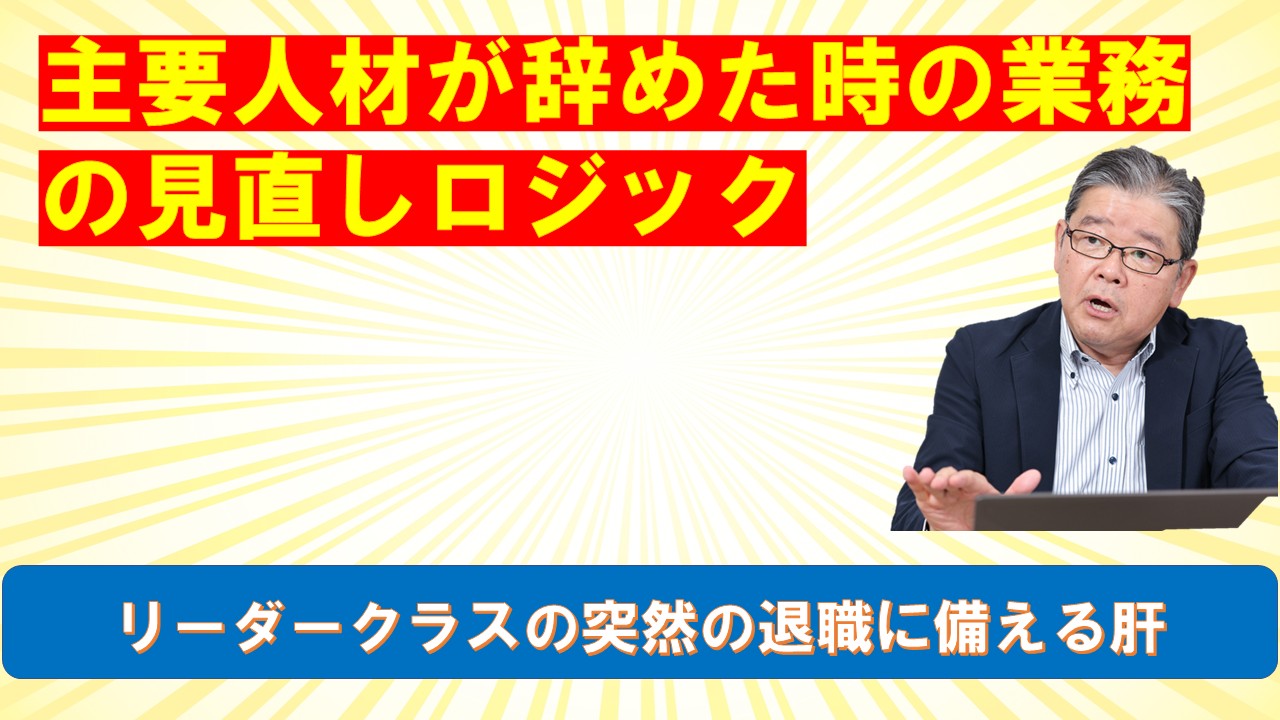

部門の中で、主要な人材や中堅クラスが退職した場合、その部門は途端に業務が回らなくなります。
先般も私が経営顧問をしている企業で、「スタッフ部門の課長が退職を決意」し、社長が説得しても退職意志が変わらない事態になりました。
その課長はマネジメントだけでなく、主要な業務も行うプレイングマネジャーです。
その課長がいなくなると、部門の業務が滞り、収益に影響することが火を見るよりも明らかです。
次の人材がいるなら、当面教育の徹底で何とかなりますが、実際に代わりができる人材がいないことが圧倒的に多いのが、中小企業です。
そこで大事な考え方が「業務の断捨離」と「キャリアパス」です。
人が退職すると、部門長は「早く新人を採用してくれ」と総務に依頼するでしょう。
しかし、今はおいそれと社員の採用ができない時代。
恐らく、経営者も総務も「今いる人材で何とか工夫して頑張ってほしい」と思っているはずです。
だから、そんな時こそ「業務の断捨離」と「キャリアパス」が重要なのです。
1,中期ビジョンと照らして業務に優先度をつける
どの部門にも「コア業務」と「非コア業務」があります。
全ての顧客や課題に対応しようとすると、この「非コア業務」を選別できません。
今のような人手不足時代では、「コア業務」には人材配置をしても、「非コア業務」は「止める」 「外注化」 「顧客利便性よりコスト優先」などの判断が必要になります。
その時の判断基準が「中期ビジョン」です。
「経営理念」を判断基準にすると、「たくさんの正しい事をしなければならない」ことになり、業務の選別に支障をきたす事が多々発生します。
だから「中期ビジョン」では、
●どういう姿を目指しているのか?
●中期ビジョンを考えると、その業務は絶対必須の「コア業務」か?
●中期ビジョンで優先度を判断したら、その業務は3番以内に入るか?
等の考え方に立つと、「中期ビジョンを考慮すると取り敢えず、○○業務はペンディングしよう」などの判断が出るかもしれません。
その時、基準は「中期ビジョン」であり、「できる人がいないからやらない」とか、「今は忙しいからやらない」と言う自部門都合での判断はしないことです。
あくまでも「中期ビジョン」で必要な業務だという大義を大事します。
と言うことは、「強み特化型経営の中期ビジョン」を先にしっかり作り込む必要があります。
2,部門間にまたがる業務は双方で改善
ある部門の突然のキーマンの退職で、他の部門や次工程に具体的な迷惑をかける事が発生します。
他部門や次工程の責任者は、「何で辞めるんだ。うちが困るじゃないか。そこの部門で何とか対応してくれよ」とクレームを入れたくなります。
しかし、この突然の退職は、いつどの部門で発生するか分からない「お互い様」なのです。
こんな時こそ、各部門の責任者が協力して「部門間連携カイゼン」を図る時です。
考え方の基本は、他部門や次工程の部門責任者が
「○○部門の課長が退職して、予定通り業務ができず困っている。我が部門では○○部門にどういうサポートをしたら、我が部門の業績悪化を最小限にできるかを考えよう」
と部下を説得することです。
そして、部門同士が話し合い、
●双方が当面確実にやるべきこと
●A部門が保留、中断してもやむを得ないこと
●B部門が協力して行うこと
●A部門がB部門と協力して取り組むカイゼン
等を細かく決めていきます。
3,ミニマムスタンダードの業務チェックリストを前任者が作成
役職者やリーダークラスが退職する場合、一部の常識を知らない社員のように「突然退職」はないでしょう。
辞めるまでにある程度の引継ぎや準備段取りを行うはずです。
その時、「人手不足を考慮した作業別業務チェックリスト」の作成を、退職するリーダーに義務付けます。
しかも、ミニマムスタンダードとして「あなたの退職後に最低限準備すべき基準で結構」と指示します。
ついでに「今やってる作業を中断する場合の代替え策、中断しても影響がない根拠」も書かせます。
要は、役職者やリーダーが辞める時が「業務見直し」の最高のチャンスなのです。
ではどうやって退職する役職者やリーダーは業務チェックリストを作成するのか?
そこは生成AIを使って、現在業務の詳細内容やポイントを書いて、頻度や優先度をAIに基準案を出してもらいます。
※6月14日の「生成AIコンサルティングチェーンプロンプト研修」でも、「生成AIを使った業務チェックリスト作成プロンプト」の経験をしてもらいました。
研修は終了しましたが、どんな内容の研修だったのか、以下からご覧いただけます。
2025.3.28【追加開催決定】6月14日(土)コンサルティング現場で使う生成AIコンサルティングプロンプト研修実施 - SWOT分析と経営継承可視化の専門コンサルタント RE-経営
4,応援人事、異動はキャリアパスをイメージして社員を説得
当面の業務のやりくりと同時に、その部門の今後を見据えた将来人事異動を検討しなければなりません。
潤沢に予備の人材がいる企業は大企業でもありません。中小企業ならさらに厳しい状況です。
しかし、その場の辻褄合わせの人事異動をした場合、納得度の低い社員が、異動の結果退職になる「2次退職」の可能性があります。
だから「君がこの部門に異動して経験を積むことが、君の将来にどう影響するか、このキャリアパスを見てごらん」と、緊急な異動でも「理屈のあった異動」である事を説明しないといけません。
そうすると、明確なキャリアパスがない企業ではこの説明ができない。
私達も中小企業の人事評価コンサルティングをする際、必ずこのキャリアパスを先に作成し、そのキャリアパスに沿った「等級別職種別職能要件書」や「職能評価基準」を作成します。
これだけ人材が流動化する時代です。
あてにしていた社員や責任者クラスが退職することが通常だと心得え、日ごろからこのような仕組みや準備をしておく時代です。
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。








