2025.9.22 監査担当者の生成AI活用技術、プロンプト技術を上げるコツ
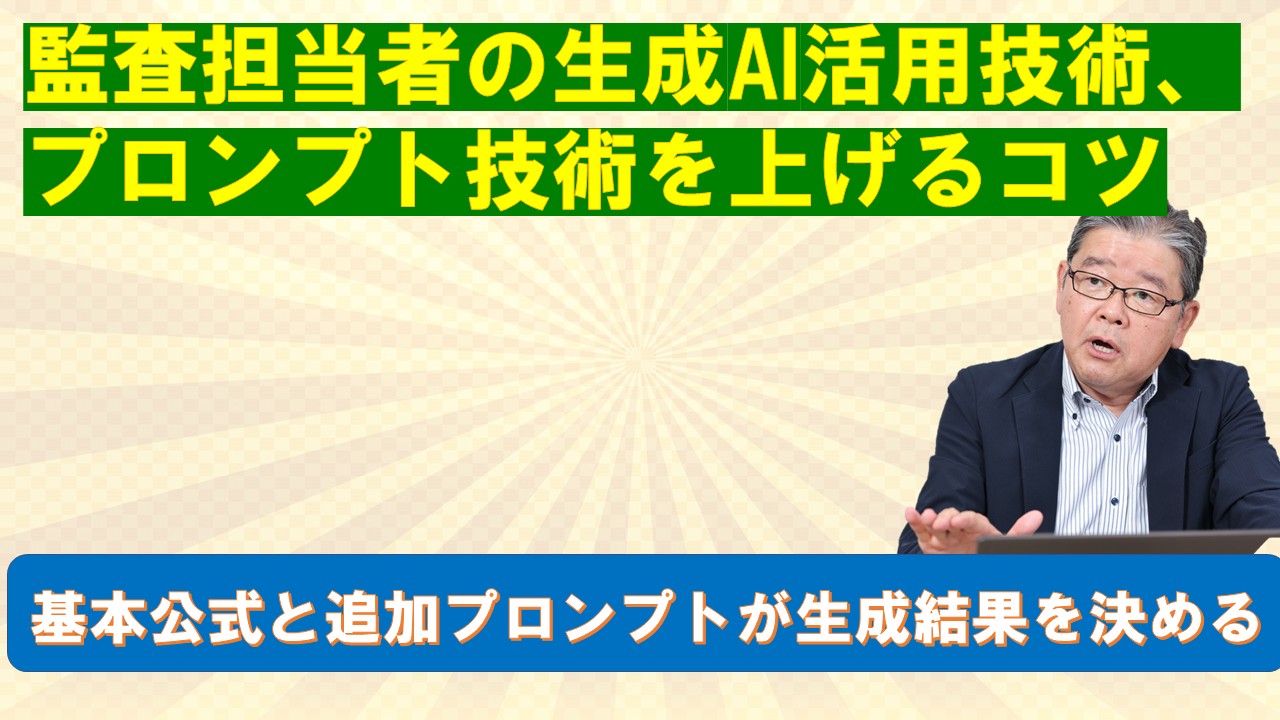

弊社が支援している会計事務所でも、監査担当者による生成AIの活用は徐々に進んできました。
ただその使用頻度やプロンプトの内容にはかなりの個人差があります。
使っていない職員はまだまだ多く、「Google検索の延長線上」の使い方しかしていません。
使っている方の職員でも「単発プロンプト」が主体で、「聞きたい事」「調査したい事」の回答を求める使い方です。
しかし、何回も言っている通り生成AIは「推論」させてこそ、その使い方の真骨頂です。
そこで今回は改めて、プロンプト技術について述べたいと思います。
1,思ったものが生成されないダメなプロンプト
ChatGPTでもGeminiでも、何かの質問をすれば、必ず何らかの答えが返ってきます。
しかし、もしあなたがこんなプロンプトを入力しているなら、「生成AIの答えって、使えない」と思う事でしょう。それは
⑴「〇〇の事について教えてください。」(抽象的すぎる質問)
⑵「〇〇をした場合、どんなやり方があるか教えてください。」(前提条件、制約条件を省略)
⑶「〇〇を出す時、〇〇も含めて、〇〇の要素を入れて、〇〇が求める内容を書いてください」(複数要件を同時に詰め込み過ぎ)
⑷「感覚的な言葉を出した質問。」(禁止事項や除外条件を曖昧に書く)
⑸「「経営計画のフォーマットを作って」(参照情報やフォーマット指定をしない)
これらのプロンプトも問題ですが、それ以上の「ダラダラプロンプト」で、的を得ない回答の連続をすることもあります。
一度AIが出した回答に対して、絞り込み質問を行わず、どんどん幅を広げる質問をしてしまう事です。
その結果がAIの回答が広範囲になってしまい、当初目的とはかけ離れた生成結果が延々と続くことです。
2,プロンプトの基本公式を知る
単発プロンプトと明確な意図を持ったプロンプトは構造が異なります。
長々とした文書でも構いませんが、下記の要素を具体的に入れたプロンプトにする事で、目的の生成物に近くなります。
⑴指示文
⑵生成AIの役割
⑶参考情報(事実情報の整理)
⑷前提条件・制約条件
⑸成果物
⑹出力形式
⑺文体指示
⑻補足指示
このプロンプトの基本公式の詳細は下記に書いています。
https://re-keiei.com/blog/generative-ai/2191-2025-3-22.html
3,重要な追加プロンプト技術
この基本公式に沿ったプロンプトであっても求める内容にならない事も多々あります。
弊社が提供している内蔵プロンプト型の「経営ナビAI」でも同様の事は起こります。
その時大事な事は「追加プロンプト」をする事です。
思った生成物にならないのは、初期入力のプロンプトがイマイチだからです。
だから生成物を見て、「それは違う。〇〇を〇〇のようにしてください」とか「〇〇を下記に条件に沿って、表を修正してください。」などと
具体的な指示をしなければなりません。
⑴出力形式の指定
例:「箇条書きで」「表形式で」など
ポイント
-
読みやすさを確保する
-
他のツールや人への転用が容易になる
-
回答の粒度が揃いやすい
⑵対象読者の指定
例:「小学生でもわかるように」「経営者向けに」「専門家同士の議論として」
ポイント
-
言葉の難易度を調整できる
-
トーンや文体が一致する
-
説明の深さを最適化できる
⑶長さ・分量の制御
例:「200文字以内」「A4一枚程度」「3段落で」
ポイント
-
冗長な出力を避けられる
-
読み手の時間に合わせられる
-
情報の取捨選択が明確になる
⑷比較・代替案の要求
例:「メリット・デメリットを比較して」「3つの選択肢を提示して」「代替案も含めて」
ポイント
-
バランスの取れた判断材料が得られる
-
視野が広がる
-
即決せず吟味できる
⑸根拠・出典の明示要求
例:「根拠を示して」「典型的な企業名を挙げて」「参考文献もつけて」
ポイント
-
信頼性が高まる
-
誤情報を見抜きやすい
-
実務や資料作成に直結させやすい
4,監査時の経営者面談での生成AIの使い方
では実際に監査時の経営者面談で生成AIをどう使うべきか?
大きく分けて2つに分けられます。
先ず1番目は「経営者面談での経営者からの課題に対して、その都度活用するパターン」です。
例えば、経営者からの経営課題や対策の質問が出たらその場でChatGPTを立ち上げて、回答を得る事です。
「先生、今〇〇に取り組んでいるが、どう思う?他社はこんな場合どうするかね」などの質問が来たとします。すると
「そうですね、ちょっとAIに聞いてみます。AIは〇〇のケースがあると言っていますが、どう思いますか?」
とAIの回答結果から、経営者との話を広げていく感じです。
2つ目は、毎回の監査後面談で生成AIを使って行うべき経営支援を決めて、取り組む事です。
例えば、決算期が近ければ、SWOT分析をして、その翌月には経営計画書を作成すると事前に経営者に伝え、それ相応の時間を確保してもらいます。
「〇〇社長、今日は来期の戦略を決める為にSWOT分析を生成AIを使って行います。じっくり取り組みましょう」と伝えて生成AIを立ち上げます。
その場合、自分でフレームを持っているならいいですが、SWOT分析の質問の仕方がよく分からないなら、内蔵プロンプト型の「経営ナビAI」を使う方がいいですね。
同じく、経営計画書も事業承継コンサルも自分なりのチェーンプロンプトがない方は「経営ナビAI」を使う方がいいでしょう。
下記の経営支援専用のプロンプトが内蔵されているので、顧問先の月次の経営支援提案を期首に決めて、行う事もできます。

「経営ナビAI」の公式サイトはこちら
今後の監査後面談での経営支援には生成AIは不可欠で、更に監査担当者のプロンプト技術が結果に大きく左右されます。
今当社では、3つの会計事務所で「生成AIプロンプト技術研修会」を実施していますが、今後はもっと増えると思います。
「プロンプト技術」を上げたい会計事務所の方は、弊社までお問い合わせください。
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。








