コンサルタントが書いた短編小説「誤認転職」③「期待が大きいスカウトの裏事情」
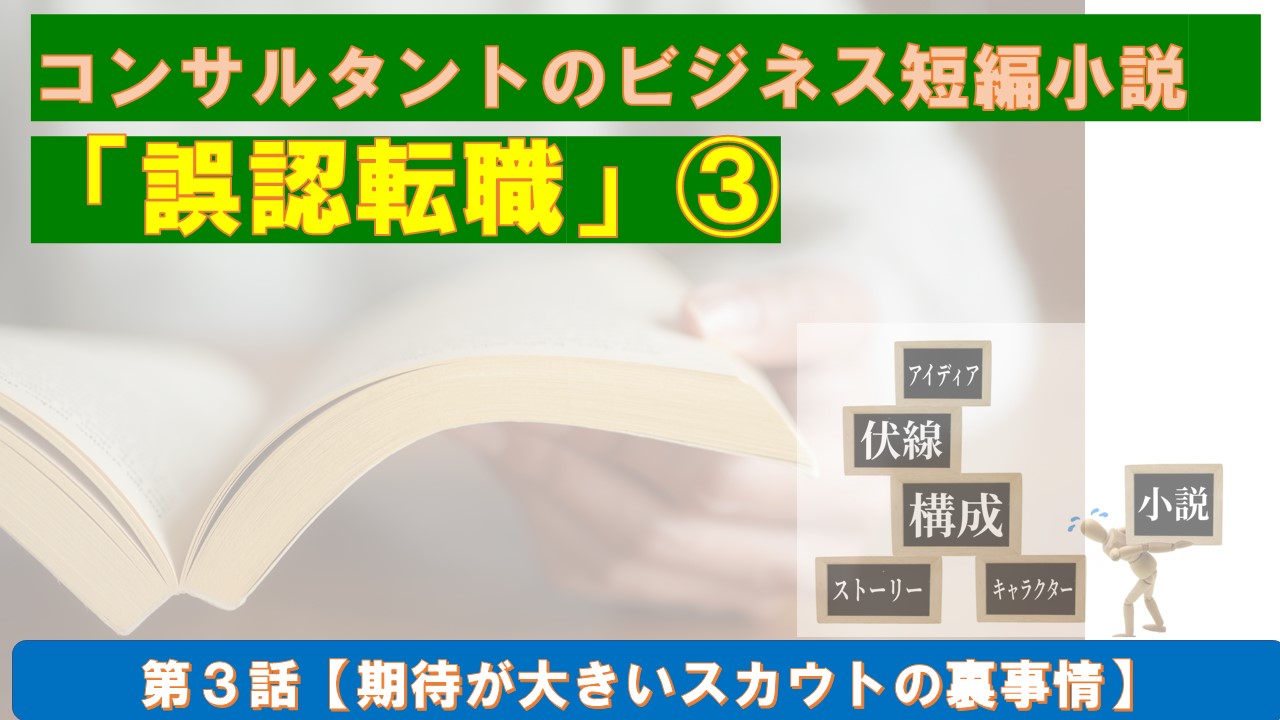
コンサルタントが書いた短編小説シリーズの3回目です。
前回までのあらすじ
ベテランコンサルタント松田は、クライアント先の田所印刷の社長からヘッドハンティングを受ける。
そして上司に相談したが折り合いはつかず、一気にヘッドハンティングを受諾することを田所に連絡した。
第4話「期待が大きいスカウトの裏事情」
田所は、松田が帰った後、専務で長男である田所康一を呼んだ。
康一は今、担当先である役所の営業から帰ってきたばかりだった。
「専務、松田先生が正式にウチへ来てくれるぞ。来月中には何とか入社できるよう頼んでおいた。」
「ああ、そうですか。」
力のない返事を康一はした。
田所はこの覇気のない後継者の態度が、いつも気にくわずに怒ることが多かった。
「専務、何だその気のない返事は。君がそうだから先生にコンサルタントの立場でなくウチの役員として会社で頑張ってもらおうと思ってるんじゃないか。」
社長室の外に聞こえるような田所の声が響いた。
田所康一は私立の大学を出て、印刷業では大手の大同印刷で営業の経験を3年して帰ってきた典型的な坊ちゃんタイプの3代目である。
上場企業である大同印刷に入社したとは言え、田所の根まわしによる在り来たりの縁故入社である。
田所は常々(専務にするには早かった)と後悔する事があったが、今後の田所印刷の後継者として早くから鍛えておいた方がよいと言う周りの進言で、28歳のときに専務取締役営業本部長にしたのだった。
能力も経験もない長男を役員にする矛盾は田所自身が一番感じていたが、そうせざるを得ない現実があった。
それは
相続税対策である。
田所印刷は歴史も古く、戦前から初代がこつこつと不動産を買い込み、当世のバブルが弾けたとはいえ、二足三文の簿価からすると大変な資産のある会社となった。
初代の逝去に伴い田所啓一は42歳で相続したが、その時は赤字が続き株価計算も不動産もそう価値がなかった為、多額の相続税を払わずに済んだ。
しかし、田所が相続してから田所印刷は堅調に成長し、株価判定も純資産法で計算すれば億を遥かに超える相続税になる。
その事が念頭にあって、とにかく株を息子の康一に委譲せねばならない。
その為には早く役員にして多額の報酬を払い、株資金を手当てせねばならないと言うお家の事情もあった。
康一にしてみれば、そんな事は頭で分かっていても毎月100万円を超える報酬なのに、銀行の株資金返済で手取りが30万円になる事がどうしても面白くなかった。
康一には理解できないレベルの話なのである。
当然経理の幹部以外、そういう事情はあまり理解していないから、一部社員から田所自身が(バカ息子に毎月100万円も払う同族の公私混同社長)と、経営能力は評価しながらも陰口をたたかれる事はしばしばであった。
田所啓一もそんな噂が社内にあることは重々承知していたが、弁解しても仕方ない事として、黙っていた。
そんな後継者である専務の仕事は営業の責任者として営業マン20名のトップであり、営業戦略から社員教育までしなければならない。
とは言っても田所啓一と二人三脚で営業を築いてきた取締役営業部長の本多と次長の佐伯がおり、通常の実務はこの二人が牛耳っていたから康一自体には大した実務責任と期待はなかった。
それでもこんな若手が30歳前から専務取締役営業本部長と言う肩書きがあれば、それを利用しようとする者も現れたり、青年会議所のメンバーである友人の後継者からの遊びの誘い、またネオン街の女性からはそれなりちやほやされてもいた。
一般的な2代目とは違う田所啓一は創業者以上の苦労をしてきだけに、3代目の康一はまさに「銀のスプーンをくわえてうまれてきた」典型であった。
そんな康一をサポートする社内ブレーンが必要だと常々田所啓一に訴えてきたのが、ほかならぬ松田であった。
松田も自分が康一のサポートをするつもりはさらさらなかったのだが、結果的には自分が提案したようになってしまったと言う皮肉な結果である。
康一は松田をどう思っていたか。
正直あまり好きではなかった。
それと言うのも、コンサルタントでありながら結局ワンマンである田所の考えをまとめているだけに過ぎないと思っていたからだ。
その事は田所印刷の幹部である本多も佐伯も康一と同じ考えを持っていた。
ただ本多にしても佐伯にしてもサラリーマンであるので、康一以上に処世術は心得えていた。
表面的には松田を否定する態度もなく、田所が松田を自分達の上の役職に持ってきたとしても反論はしない。
しかし、康一は若いがゆえに顔に出るのである。田所はそこを見のがさずに康一をつめたのだった。
康一は田所啓一に怒られながら、ぼそぼそと質問をした。
「松田先生に何をしてもらうんですか?」
「君の補佐だ。しかし役職は取締役副社長できてもらう。いろいろな経営企画を私と一緒になって取り組んでもらうつもりだ。だから君が専務らしい仕事をしないとバンバン叱咤されるぞ」そう言って、自室へ戻っていった。
十一月に入って最初の経営会議が開かれた。
松田にとってはコンサルタントとして最後の会議指導である。
経営会議のテーマは年末の繁忙期の生産現場の対応と営業の年末追い込みであった。印刷業界は年末と入進学シーズンに営業の山場を迎えるのだ。
もとより松田の指導によって田所印刷は毎年4月事業年度に合わせて単年度の経営計画書を作成し、4月1日には全員で経営方針発表会を行っている。
会社の方針と各部門の具体策を調整して全社一丸となって進む事を合い言葉に今年の経営計画書で2年目である。
その経営計画書にも十一月の商材対策と目標売上、目標利益は記されている。只それが計画通り進行しているかをチェックし、経営改善の話し合いをする場が経営会議となっている。
出席者は社長の田所、専務の康一、営業部長の本多、次長の佐伯、工場からは工場長の右田、印刷課長の笹山、そして松田が出席して進める。
松田はいつになく専務の康一と工場長の右田が元気がない雰囲気を察知した。元々この両名はいつも覇気がないが、今日は特にひどいものを感じた。
議長である田所が議論を進め、各種の決定事項と検討事項を要領よくまとめ、(と言うよりワンマン経営者の発言に他の幹部が発言しないだけなのだが)、松田にいつものようにこの経営会議での問題点や指摘事項を問い質した。
「先生、何かありませんか。」
突然田所から意見を求める質問があった。
こう振られて松田は時として困ることがある。
と言うのも、田所がどういうコンサルタントの指摘を期待しているか、が見えない時がたまにあるからである。
通常は事前に経営者と打ち合わせをしているのだが、今回は松田のスカウトの話に時間を取られ、肝心の会議の事前の煮詰めをしてなかった。
松田が経営指導をするやり方はその会社のトップの考え方に合わせるので、どうしても経営者に迎合してしまうのである。
新日本経営開発の高宮と加納が指摘していたのは正にその事であった。
「12月の受注ベースがこの3年間で一番少なくなっていますが、専務はどのうような対応策を考えているのですか?」
松田はデータを見ながら、質問した。康一はまた(俺にばかり質問しやがって)と嫌な思いをしつつも答えた。
「大口顧客の受注伝票が上がってない結果です。受注自体には問題ありませんので、今週中には来月ベースが昨年並みになると思います。」
と言って本多の顔を見た。本多は黙って俯いたままだった。
「昨年並では困ります。経営計画では3億円の売上を見込んでいるんですから、その差額対策を具体的に詰めないと目標達成はおぼつきませんよ。下半期に入って連続で経営計画どころか、昨年対比も下回ったままが現実でしからね。」
康一はそんな事くらい松田に言われないでも分かっている事だと、伏し目がちに松田を睨んだ。そして、多少感情的に、
「先生も知ってのとおり、改正消費税以降の商業印刷の発注高が減少しています。これはわが社だけでなく他の同業者もウチよりもっとひどい。我々はそれなりに健闘しているつもりです。」
康一は言ったあと、しまったと言う表情したが、後の祭りだった。
「お前はわが社を潰す気か。営業の責任者がそんな弱気でどうする。本多部長どうなんだ。君も専務と同じ見解なのか。」
松田が答えるチャンスがない程、田所は議長と言う立場を忘れ、営業に喰ってかかった。
「そういうわけではありませんが、受注単価の厳しさや数量制限があるのは事実です。その中で生産部と共同で進めてきた納期管理システムも少しずつ成果を上げてますので、昨年はクリアーできると思います。」
本多はこう答えるしかなかった。
「とにかく、専務のように後ろ向きな議論は困る。十二月はなんとしても3億に乗せてくれ。」
田所はそういって鉾先を納めた。
悔しいのは康一であった。しかし、松田に反論しても田所がいる限り逆襲にあうことは見えている。だから黙っていた。
「今のは決定事項でよいですね。」
皆の返事はなかったが、松田は書記の総務部長に目配せをした。
ひと呼吸おいて田所が話始めた。
「1年間コンサルタントとしてお世話になった新日本経営開発の松田先生には今月限りで指導をお断りする予定だ。」
一瞬皆が驚いたように田所を見た。田所はそんな視線に構わず、続けた。
「来月からはわが社の取締役副社長として正式に働いてもらう。皆そのつもりでよろしく頼む。それではこれで経営会議を終わります。」
松田と田所を残して、他はそそくさと会議室を後にした。会議室で二人きりになった所で、田所は松田に話し掛けた。
「先生、いや副社長、専務の教育を宜しく頼みますよ。私の育て方が悪かったでしょうけど、自己本位で経営と言うものを全く理解してない。3代目で潰れる会社が多いですがウチは絶対そうならないようにしますから、力を貸して下さい。」
田所は再度丁重に頭を下げた。
「こちらの方こそ宜しくお願いします。」
と松田も深々と頭を下げた。
中小企業の経営会議と言うものは、話し合いがなされても、およそ経営者の考えをゴリ押しする独断場か、経営者以外が仕切った合議制かである。
田所印刷は実力社長のワンマンであるが故、どうしても経営者の独断場にならざるを得ない。
しかし、そんな中で松田はこの2年間に会社らしき仕組みを幾つか導入してきた。
一つが経営会議の報告システムと決定事項システムである。経営会議を円滑にすすめるため誰が、何をいつまでに、どのようにと具体的に決定事項を出すことである。
会議運営に慣れてない田所印刷も松田のお陰で会議システムと報告システムが経営層、部門長層、現場職長層と層別に進められるようになった。
二つ目が、年度の終わりに来年度の経営計画を作成し、計画経営を実施する事である。
計数だけでなく、部門毎に具体策を担当者別に作成する事で経営会議や部門長会議では議題の半分はあらかじめ決まっているのである。
それは管理者にはどんな報告が期待されているかが分かるのである。
三つ目が人事考課制度の導入である。ただしこれはシステムは作ったが不満不平なく運営されている訳ではなかった。
TOPとの最後の挨拶
「松田君、来週の金曜日の午後は在社してるかね。」
松田が出た電話の相手は新日本経営開発の社長である佐藤であった。
「引き継ぎも一段落していますので、在社してる予定ですが」
松田は行動手帳を見ながら答えた。
「なかなか忙しくて、君とじっくりはなす機会がなかったんでね。退職前に話したいと思ってね。」
「分かりました。お待ちしています。」
と言って電話を切った。
松田にとって、直属上司である高宮は好きでなかったが、佐藤は尊敬している経営者である。
佐藤は全国の事業所を毎月転戦し、セミナーやらクライアントへのコンサルティングやらで社員と言えどもアポイントなしでは面談さえできない状態であった。
5日後佐藤が中央事業所にやってきた。
松田と話す前に高宮との面談が設定され、その後に松田の出番だった。
松田は佐藤と高宮が何を話しているか多少気になったが、どうせ辞める身分だし気にする事はないと開き直って待っていた。
佐藤と高宮は応接室に入っていった。
『松田君から手紙が来たよ。辞表だけでなく、退職に至った経緯を率直に書いていた。』
佐藤が応接室のソファーに座るなりいきなり切り出した。
「ほう、そうですか。なんと書いていました」
高宮が興味深気に尋ねた。
「君のマネジメントの問題や、自身の糖尿病の問題、そして受注を強制される事への反発と不満が中心だったな。」
佐藤はかいつまんで手紙内容を答えた。
「結局彼はコンサルタントの受注活動から逃げたいのが本音なのです。形では室長としていますが、どこに転勤させても1回もマトモな受注がなかった。
だから部下から否定される。この繰り返しでわずかなクライアント先でコンサルティング三昧をするわけです。
私も彼から辞表がでた時正直ほっとしました。幹部が受注をしないコンサルタント会社は長く持ちませんからね。」
やはり高宮は冷静に感想を述べた。
「確かに君の指摘取りだ。だがどうしたものかね。私も田所社長は良く知っているが、あの浮き沈みの激しい性格に松田君が耐えられるかね。松田君は社員教育を中心にやってきたのだろう。本格的なコンサルティングはあまりしてない筈だが。」
本気で松田を心配している佐藤の言葉が曇った。
「それは私も何度も話しましたが、彼も42です。自分の分別はつく筈です。もし失敗しても本人の問題で自業自得として扱うしかないと思いますが。」
「それはそうなんだが。相変わらず君はドライだね」
高宮は優秀な男だが、佐藤から見れば、(もう少し優しさや情愛が社員に対してあればバランスのとれたビジネスマンになれるのに)といつも感じていた。
高宮との話は終り、佐藤の前から高宮は退出した。
「失礼します。御無沙汰してます。」
挨拶をしながら松田は応接室に入り、待ち構えていた佐藤に一礼をした。自分の会社の社長に、御無沙汰と言う挨拶も本来はないが、いつも飛び回っている佐藤には適した社内挨拶だった。
「いよいよ来週で最後だね。少し寂しくなるな。先方とは仕事内容や責任ついては細かく詰めはできているのかい。」
佐藤の語り口は高宮と全く違って、優しく思い遣りのある雰囲気だった。
「長い間お世話になりました。お陰さまで、田所社長が大きな方針をおっしゃって頂きましたんで、仕事や責任も大体分かっています。」松田は元気よく答えた。
「君の健康面は確かに気にはなっていたが、なんせこのコンサルタントと言う仕事は自己管理=セルフコントールしかないからね。私も社長として辛いところなんだ。
私も正直心配しているんだが、田所社長の性格は私も知っている。君が担当する前には高宮君も私もつき合っていたからね。あの人は性格の激しい人だし、気に入ればトコトン仲良くなれるが一度不信感や猜疑心を持つともう修復が難しい方だから。」
「はい、私も分かっているつもりです。ですが取締役副社長でそれなりの権限を頂き、私を信頼して頂けるならそれなりに粉骨砕身努力する事は厭いません。」
松田は、佐藤に素直に返事する自分が不思議だった。
しかし、佐藤にはその返事が悲しくて、空しくて仕方なかった。(だったら何故、ウチで一生懸命頑張らないんだ。いい年して青い鳥症候群でもなかろうに)心の中で思ってしまった。
まるで青い鳥症候群だ。
青い鳥症候群とは、自分にはもっと自分に合った仕事や環境があると信じ、転々と仕事や環境を変えていき、挙げ句の果てには、自分の努力不足を棚に上げて環境を、他人を恨んで生きる人達のシンドロームの事である。
辞めていく連中はいつも自分が正しく、会社上司が間違っていると言う。そして、引き継ぎもろくにできず、新しい会社の事ばかり考えている。だから、引き継ぎが終了したらあまり期間を置かず、退職するのが望ましい。辞める人間にはもう今の会社の事など頭にないのが常である。
また、佐藤は思った。
(高宮の指摘通りだ。松田は自分の置かれた状況を客観的に見ていない。これは失敗する転職になるなあ)
と永年のコンサルタントとしての勘がそう思わせた。
しかし、もう言っても仕方ないことだと即座に割りきり、話を続けた。
「とにかく頑張って、さすが新日本経営開発出身の人は違うなあと言ってもらえることが君の評価だし、前職を評価してもらう事だからね。」
最後は佐藤から激励の握手を求め、松田は長い間のお礼を言って、応接室を後にした。
一人になって佐藤は、これから松田に降り掛かる幾つかの災難や試練、厳しさを憂慮したが、最終的に松田の持つ運命がそうさせると考え、その時点で佐藤の松田に対する関心は消え去った。
次回第4話「新天地へ入社、いきなり四面楚歌」
こちらのページもいかがですか?
無料電子書籍ダウンロード
「これを無料で渡すんですか?」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供!各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
コンサルティング現場実例ノウハウ
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか?」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。








